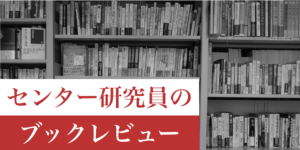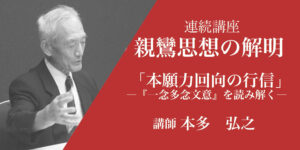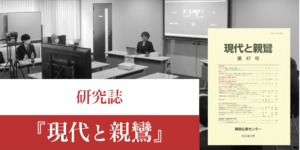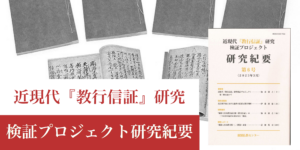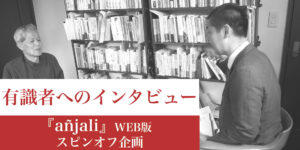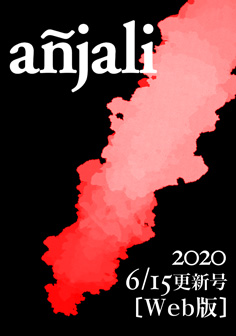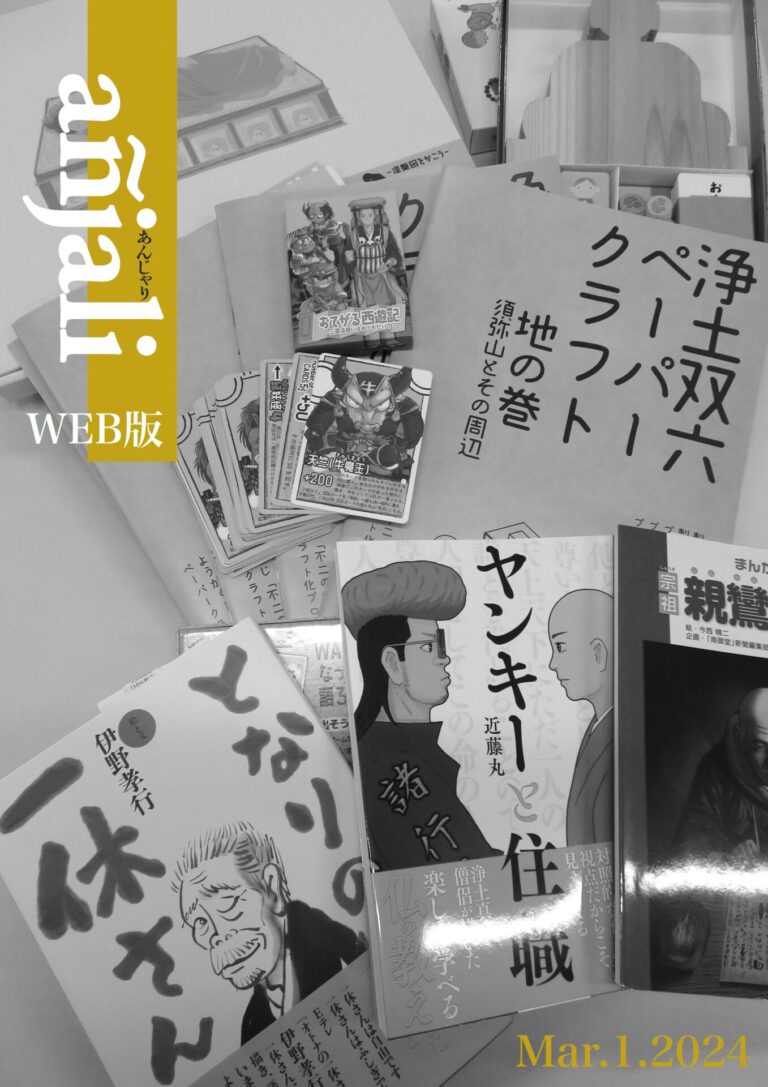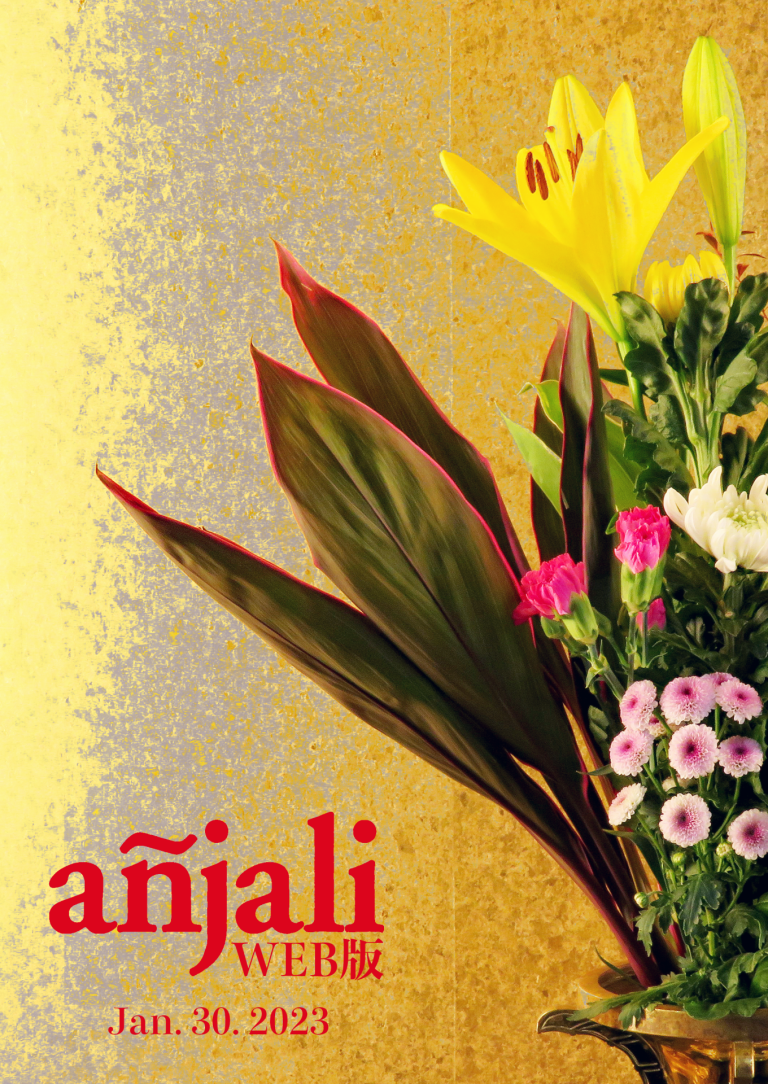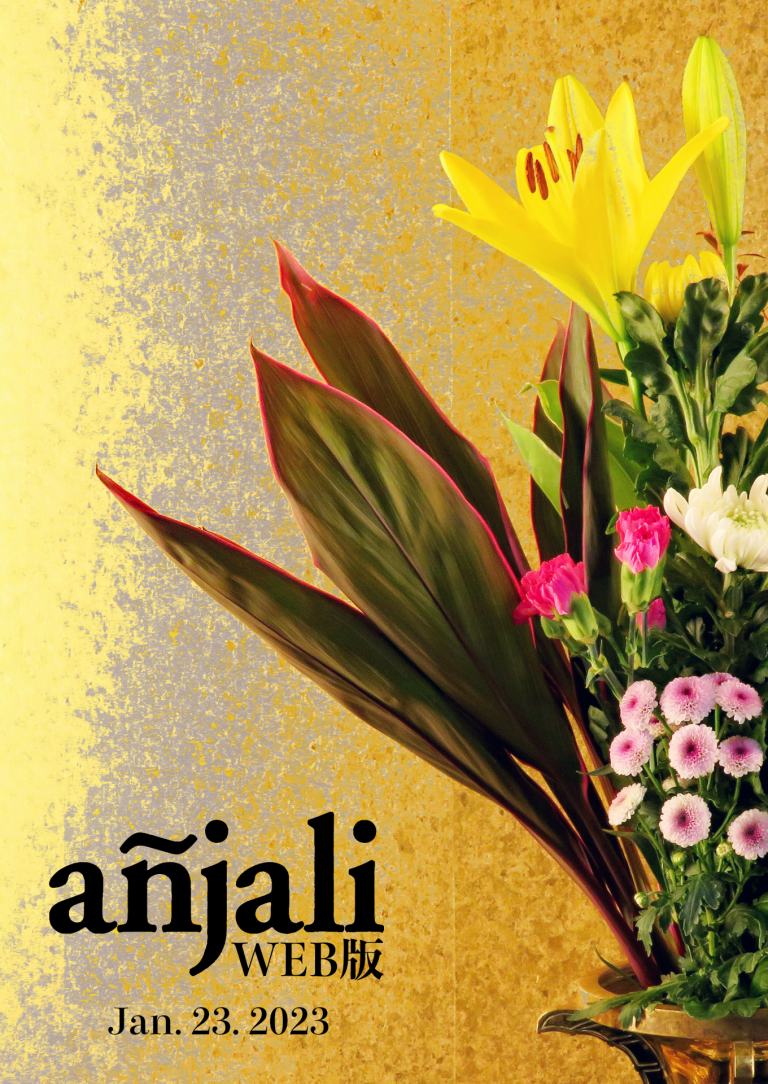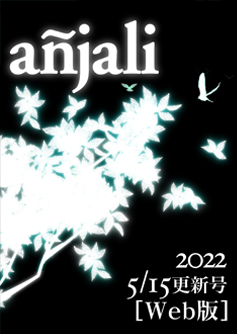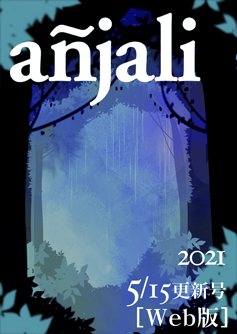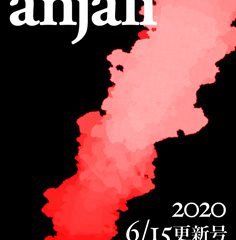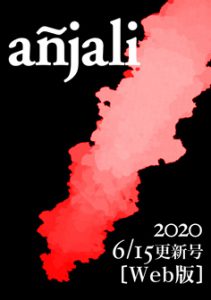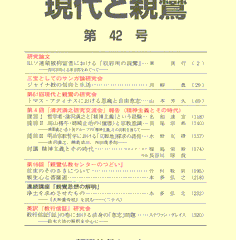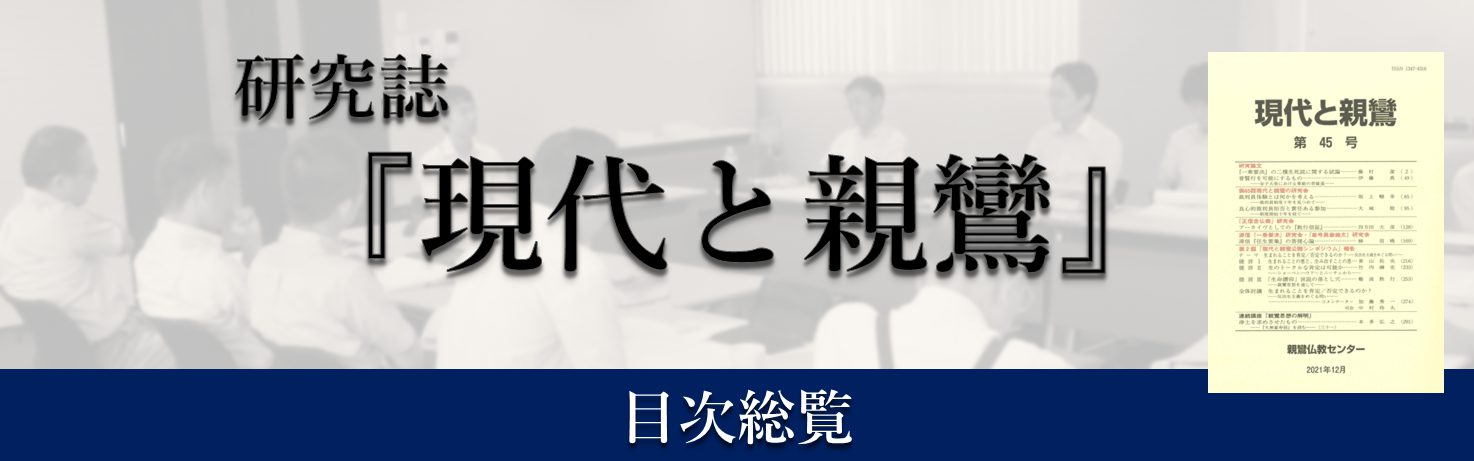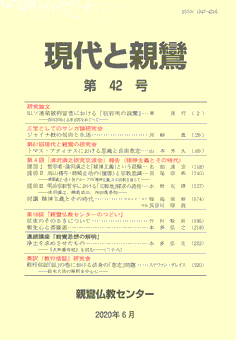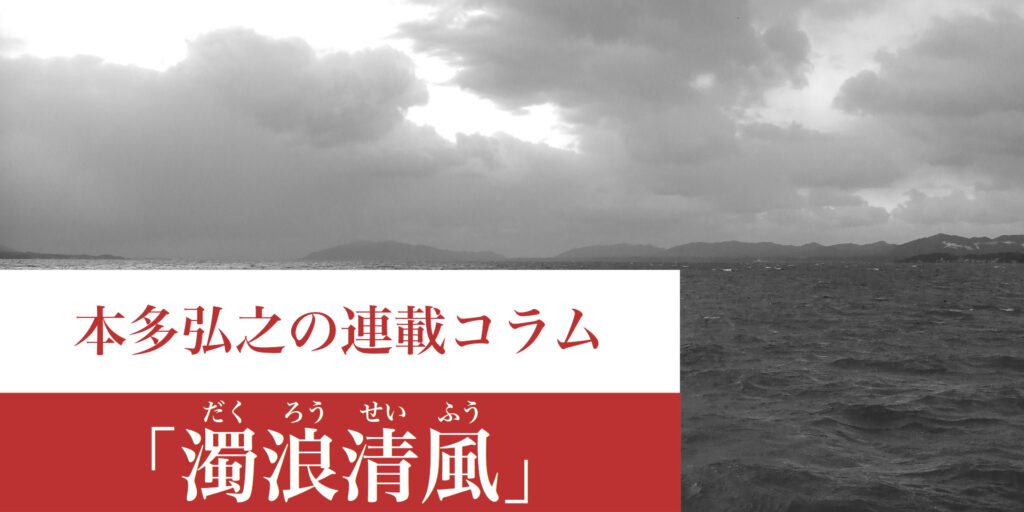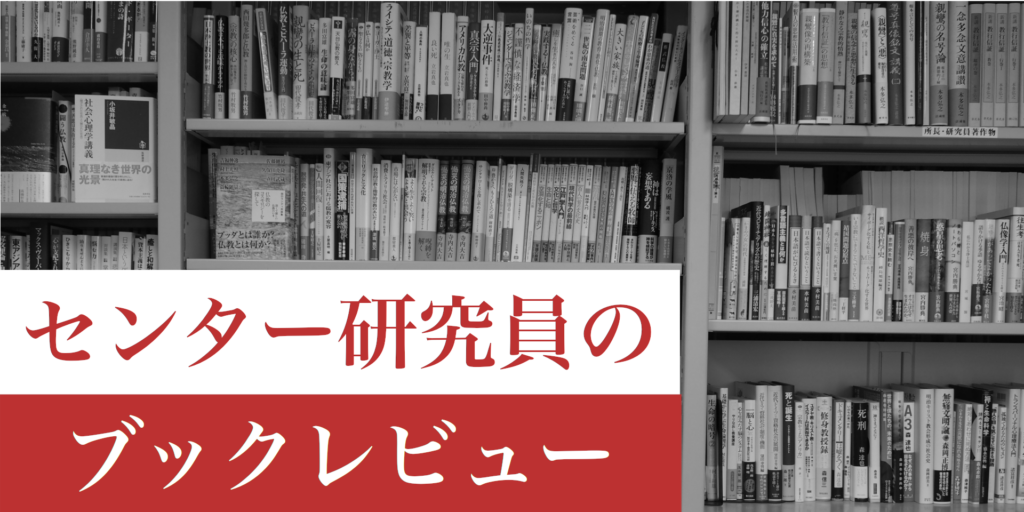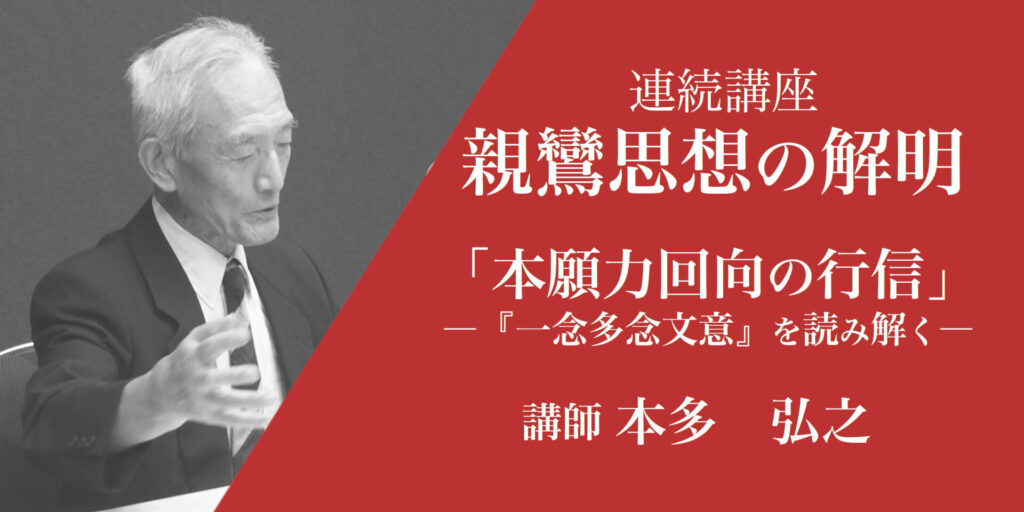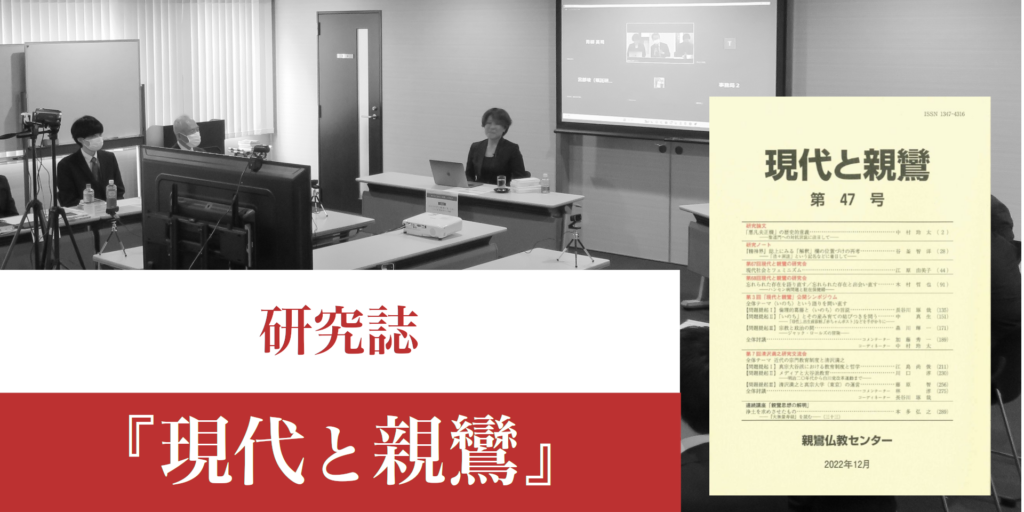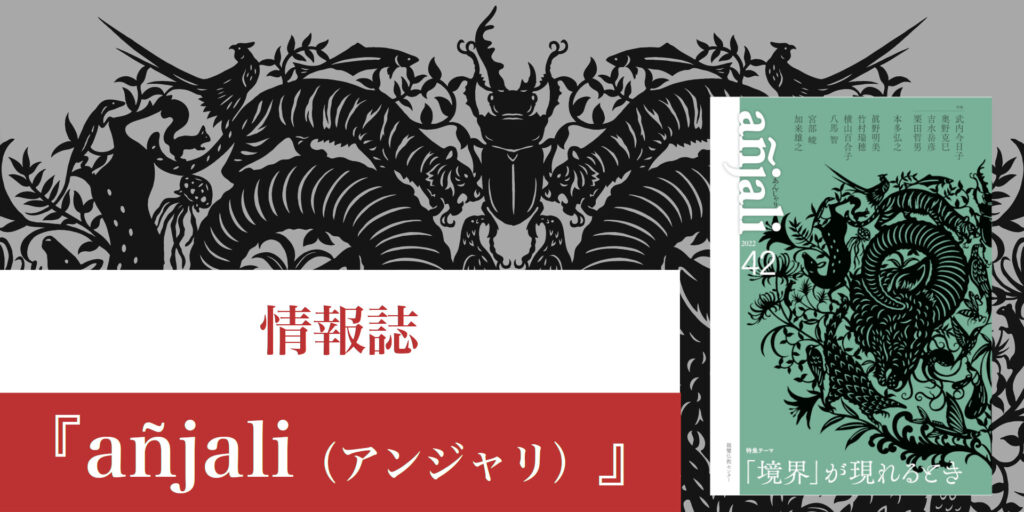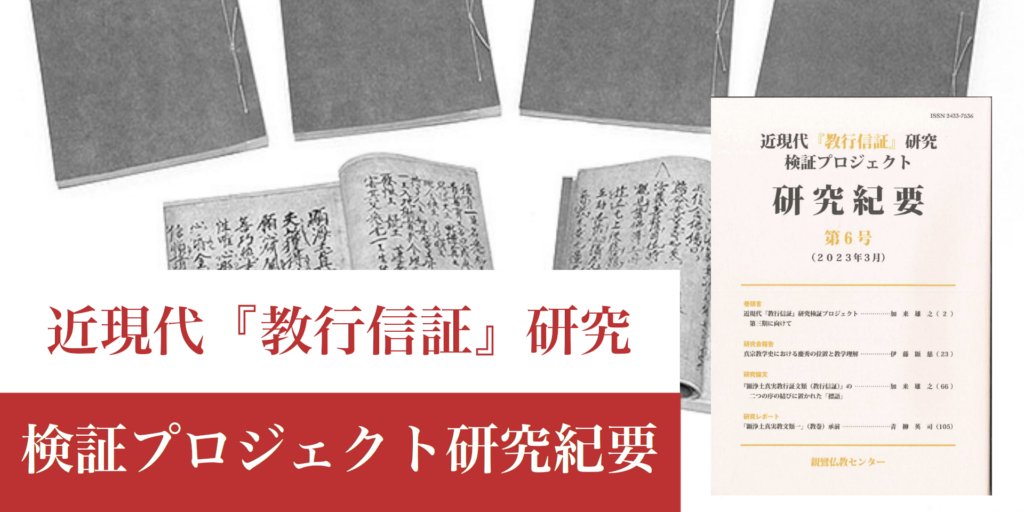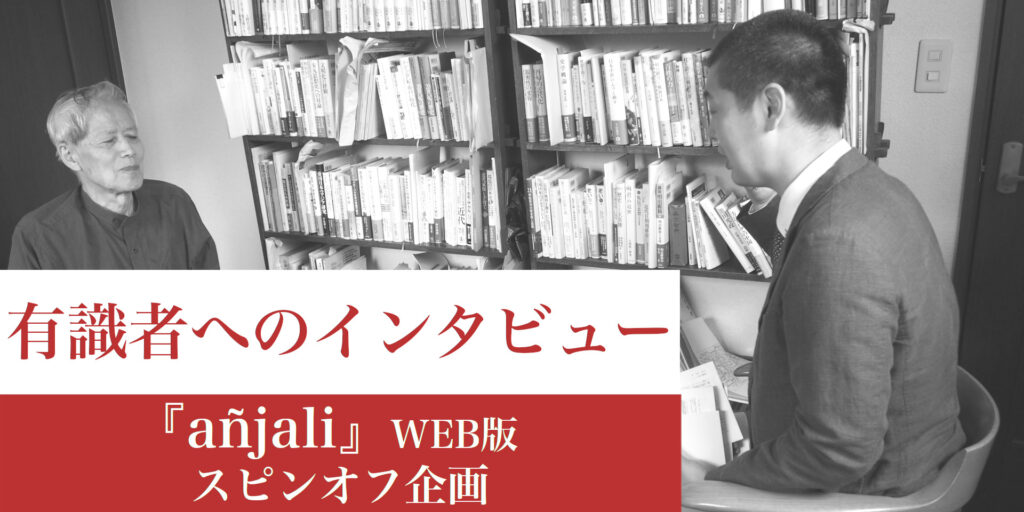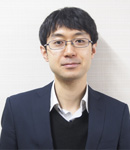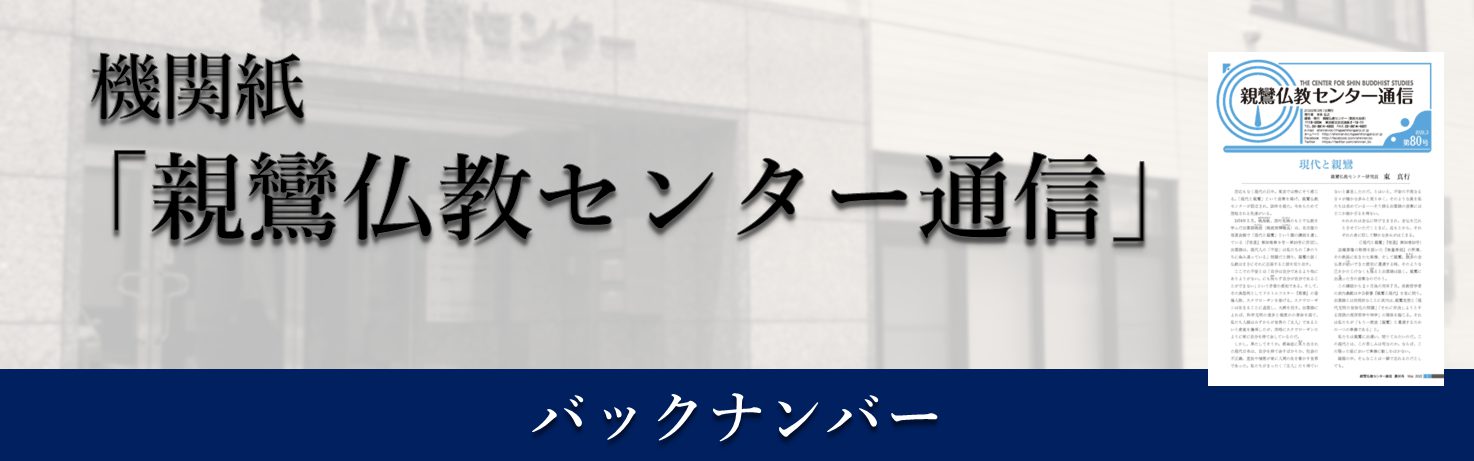長谷川琢哉

親鸞仏教センター嘱託研究員
長谷川 琢哉
(HASEGAWA Takuya)
コンビニエンスストアで 350mlの缶ビール買って
きみと夜の散歩 時計の針は0時を差してる
“クロノスタシス”って知ってる? 知らないときみは言う
時計の針が止まって見える現象のことだよ
きのこ帝国「クロノスタシス」(2014年)
きのこ帝国というバンドの「クロノスタシス」という曲をたまたまインターネットで聞いたのは、昨年末のことだった。スムースなR&B調の曲が自分の好みにあっていたことからまずは惹かれたのだが、しかしこの曲が私の心に強く残ったのは、その歌詞によるところが大きかった。
この曲が描いているのは、カップルが休日の真夜中に散歩をしている情景である。二人は缶ビールを飲みながら家に帰っているところで、女性の方(ボーカルが女性なのでそのように仮定しよう)は、この夜の散歩になんだか夢のような心地よさを感じている。しかしその時突然、彼女は「クロノスタシス」って知ってる?と相手に問う。そしてそれを知らなかった相手に対して、「時計の針が止まって見える現象のことだよ」と説明する。そういう曲である。
「クロノスタシス」というのは、動いている時計の秒針をふと見た瞬間、その時計が壊れているかのように止まって見える錯覚のことである。これは錯覚であるから、もちろん秒針はすぐに動き出すだろう。しかしその錯覚が生じている瞬間は、時計の針が永遠に止まってしまったかのように感じられる。つまり、ほんの一瞬の中に永遠(の錯覚)を感じることが「クロノスタシス」であるとも言えよう。
そしてこの曲のおもしろさは、恋愛の一場面を描写するために「クロノスタシス」というモチーフを用いているところにある。恋人同士の心地よい夜の散歩。語り手である彼女は、この幸福がずっと続くかのように一瞬感じた。しかし彼女はまさしくその瞬間に、相手に「クロノスタシス」って知ってる?と問うのである。ということはつまり、彼女は気づいていたのだ。永遠にも感じられる今この瞬間の幸福が錯覚であり、すぐに移ろってしまうものであることを。
さて、この曲に私が興味を惹かれたのは、ちょうどその頃、写真家・野村佐紀子が碧南市藤井達吉現代美術館で開催した個展(「野村佐紀子写真展“GO WEST”」)に合わせたレクチャーを行う機会があったからだ。野村佐紀子は長年、荒木経惟のアシスタントをつとめた写真家であり、人物ポートレートや男性ヌードを得意としている。また、荒木の作風を受け継いでか、野村の写真の多くには、生と死を見つめる独自の視線が感じられる。例えば野村は写真家としてのキャリアの当初から、後に亡くなった男性モデルを撮り続けており、その出会いと別れが自らを作家として成長させたという。生の裏側に常に存している死。生を描くことは死を描くことでもある。ごく当たり前のこうした事実を私たちは忘れがちであるが、野村の写真を見ていると自然とそうしたことが思い起こされる。
野村の個展が開かれた碧南の美術館は、ちょうど清沢満之の自坊である西方寺の目の前に位置している。それを機縁として、今回の展示で野村は清沢満之に関連するいくつかの新作を撮り下ろした。当時は不治の病であった結核を患っていた清沢満之は、文字通り血を吐きながら自身の信仰についての思索を続けた宗教哲学者である。その意味で、写真家としての野村の作風と、モチーフとしての清沢満之の相性は良いように私は感じた。展覧会で私は野村の作品を数多く見たが、直接清沢に関係する写真以外でも、深いところで何か通底するテーマを十分に感じさせるものだった。
野村の個展に合わせたレクチャーでは、私は清沢満之について話すように依頼されていた。しかし写真の門外漢である私が何を話せばよいのか。レクチャーの1週間程前、ちょうどそのことを考えている頃に、たまたま私はきのこ帝国の「クロノスタシス」を聞いたのだった。何となくこの曲が頭から離れず、そしてどこか野村展のレクチャーで自分が話すべきことと関係があるような気がしていた。考えはまとまらなかったが、配布資料に歌詞の一部を引用して持参した。
そして当日。私は来場した一般の方に向けたレクチャーで、主に清沢満之の生涯と思想、信仰を紹介した。数多くの挫折に見舞われながら、清沢満之がいかにして他力信仰を獲得するための思索を行ったのか。そして失意の底にあったはずの死の直前に、いかにして清沢は「「現世に於ける最大幸福」を感じる」と語りうるほどの境地へと至ったのか。そうしたことがレクチャーの主題となった。
一通り話し終わった後、私は最後に「クロノスタシス」について言及した。この上なく幸福な瞬間に、しかしその幸福が実は錯覚であることに気づいていることを歌った曲として。そしてそれは逆の意味で、清沢満之の信仰にも似ているような気がするとも。私が考えていたことが参加者の方々に十分伝わったかはわからないし、私自身も完全には言語化できていなかったように思う。しかし私の話を受けてキュレーターの方が、写真という芸術の特徴は一瞬を永遠に切り取ることであって、それはクロノスタシスに似ているところがある、と補足してくださった。一瞬と永遠、絶望と幸福、あるいは生と死。その反転は際どく、ある意味では錯覚のようなものなのかもしれない。しかし少なくとも清沢満之は、不幸のどん底で現世の最大幸福を感じるという信仰の逆説が、本当に自分の身の上に生じていると確信していたのだ。そして今になって思えば、野村の写真から私が感じたのも、生の一瞬を切り取ることによって、そこに死の永遠を刻みつけるといった、写真の逆説的な営みそのものだったのかもしれない。この逆説、反転がいかなるものであり、いかにして実現されるのかということ。野村展を通して私の心を捉えていたのは、おそらくこのことだったように思う。そしてそれは、どこかクロノスタシスに似ているのかもしれない。
――そして現在。あのレクチャーからわずか数ヶ月の後、私たちの生活は一変してしまった。ついさっきまで健康だった人が亡くなることもあれば、安全だと思っていたことの多くが危険なものにもなった。その反転はあまりにもたやすかった。生と死は紙一重、あるいは一体であるということが、日々、現実的に突きつけられている。私たちは平穏な日常が永遠に続くものだと思いこんでいたが、しかしそれこそが錯覚だったのだ。
とはいえ、私たちの生活が根本的に儚く移ろいやすいものであるということは、仏教が昔から説いてきたことでもある。そしてその上で、なにか確かで、永遠に続くようなものがあるとすれば、それはこの儚く移ろいやすい生活のただ中においてのみ、現れ出るに違いない。あるいはほんの一瞬、錯覚のように。
(はせがわ たくや・親鸞仏教センター嘱託研究員)
他の著者の論考を読む