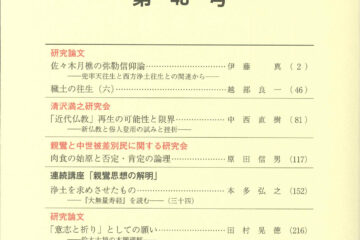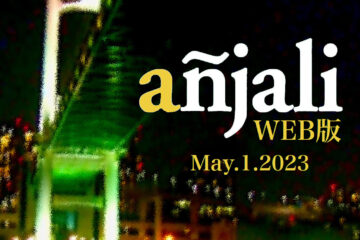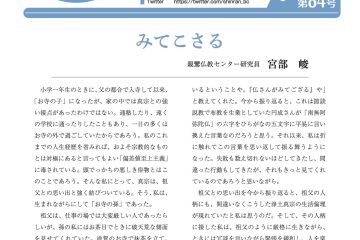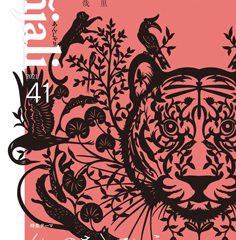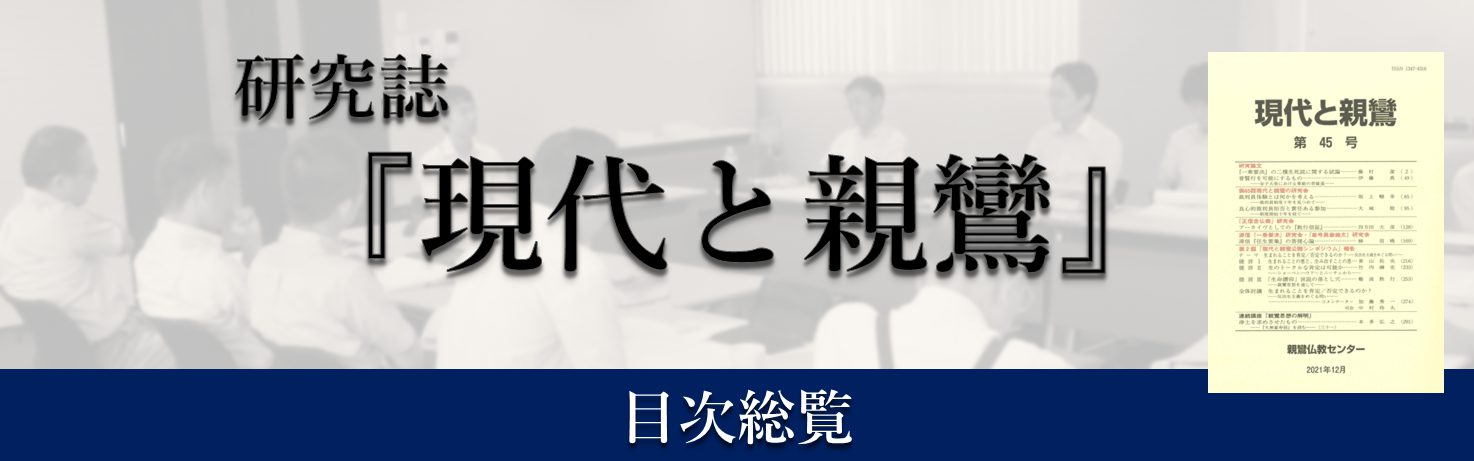
越部良一 掲載Contents
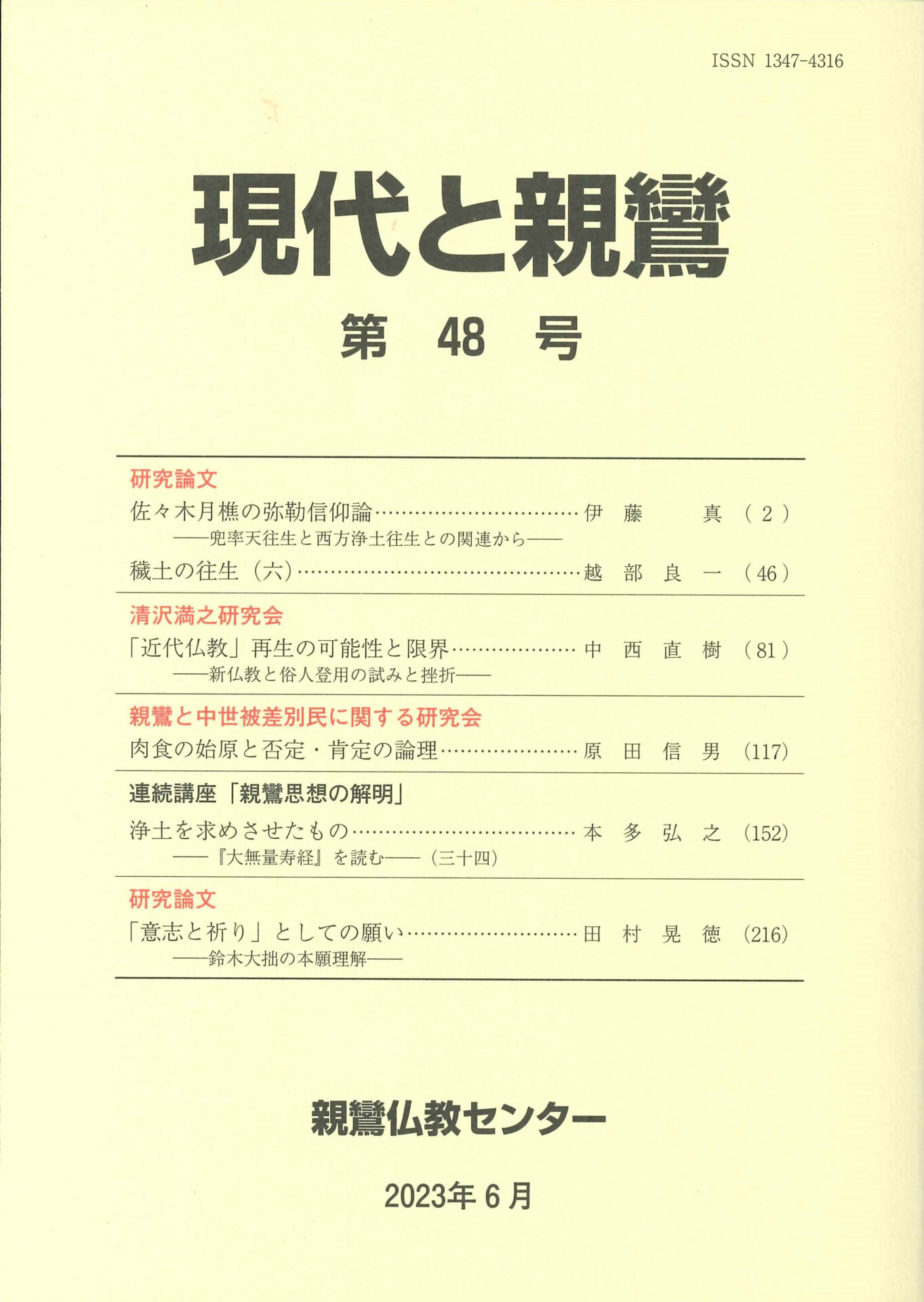
■研究論文
■ 清沢満之研究会
中西 直樹 「「近代仏教」再生の可能性と限界 ―新仏教と俗人登用の試みと挫折 ―」
■ 親鸞と中世被差別民に関する研究会
原田 信男 「肉食の始原と否定・工程の論理」
■ 連続講座「親鸞思想の解明」
本多 弘之 「 浄土を求めさせたもの ――『大無量寿経』を読む ―― (34)」
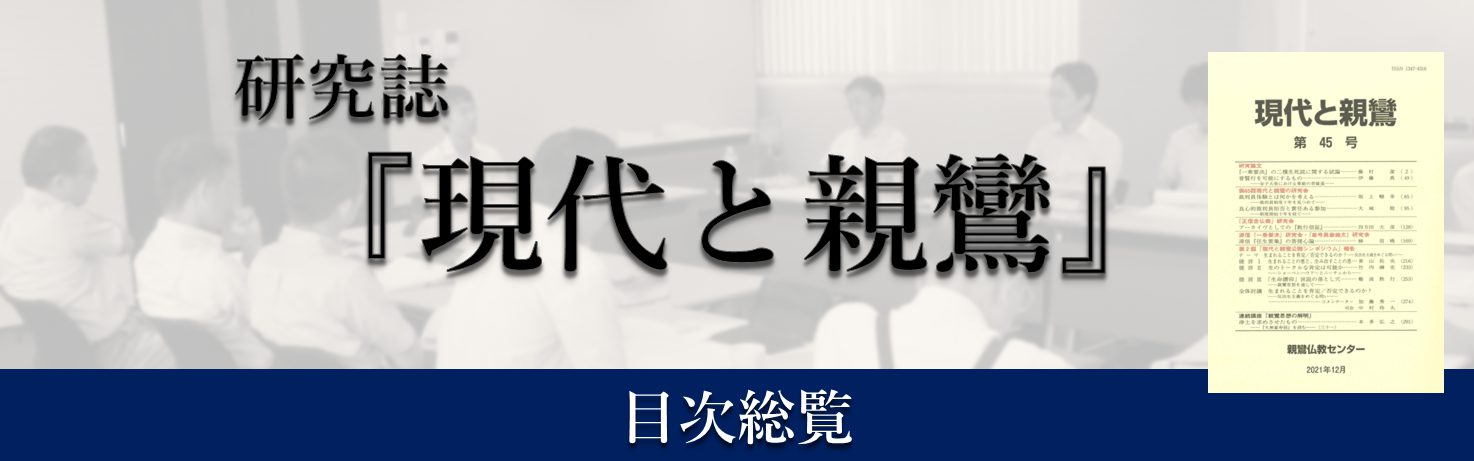
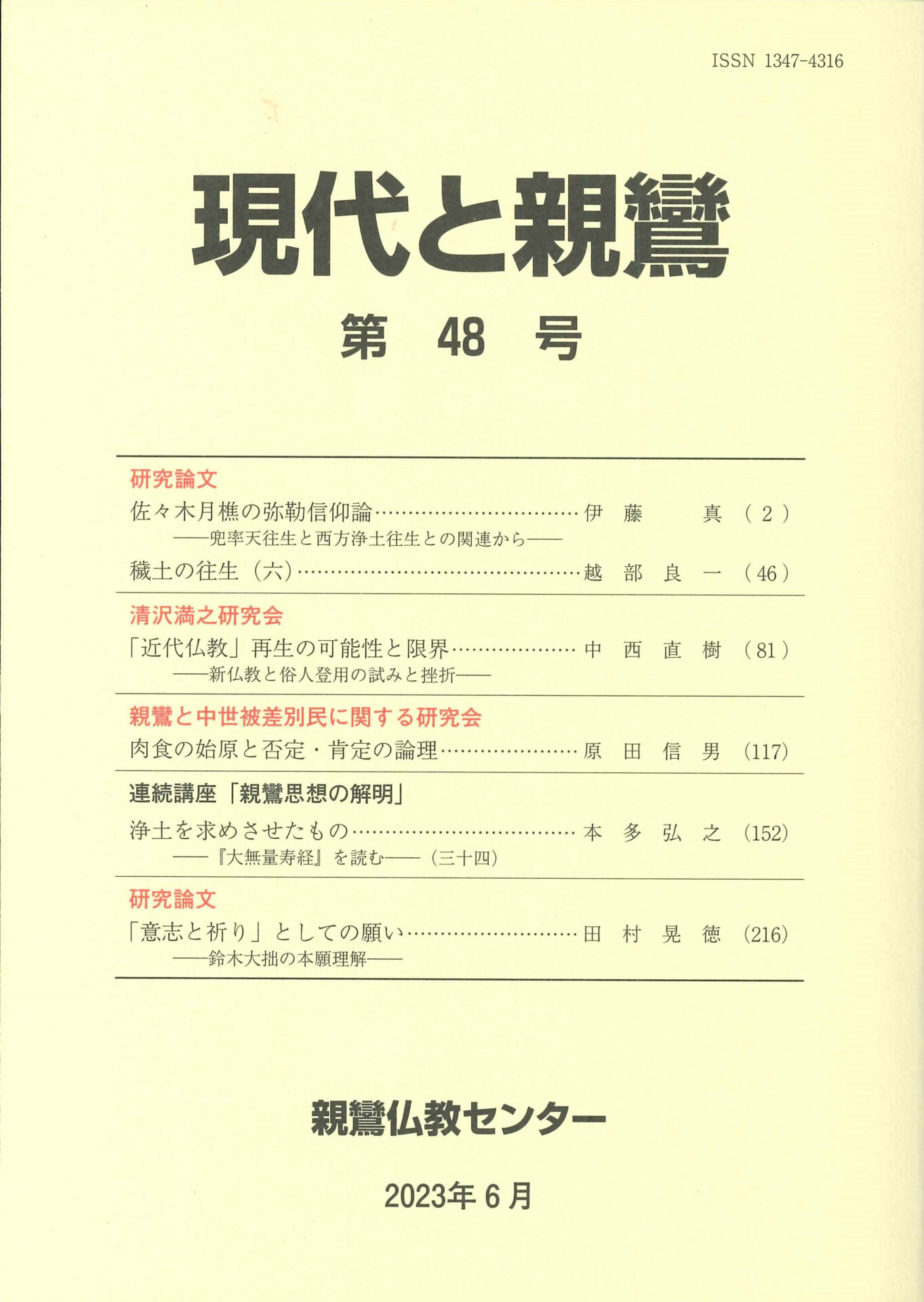
中西 直樹 「「近代仏教」再生の可能性と限界 ―新仏教と俗人登用の試みと挫折 ―」
原田 信男 「肉食の始原と否定・工程の論理」
本多 弘之 「 浄土を求めさせたもの ――『大無量寿経』を読む ―― (34)」


親鸞仏教センター嘱託研究員
越部 良一
(KOSHIBE Ryoichi)
私はいったいいつから哲学し出したのか、という問いに、私はこう考えることにしている。それは12歳の時、ビートルズの「A Day in the Life」に出会った時であると。
大学教授であったカール・ヤスパースが、高齢になって大学を退職した後、自身の仕事場とした大学というものを回顧してこう述べている。「大学の理念というものを、大学入学以来、真剣に受け止めてきた一人の男が、この理念がほとんど通用していなかったドイツの大学企業体に入り込んだのだった」(ヤスパース『運命と意志』)。
精神的なものを求めて動いてゆきながら、精神を窒息させる状況に入り込む。精神の開放を求めて動いたのか、精神を閉じ込めるために動いたのか、わけがわからない。どこにでもあることだ。だから人は、その動いた初心を忘れないようにしなければならない。
次の表現は、こうした初心を示そうとしているのだと、私は見る。
「状況の中で状況と共に絶えず流転しながら、私がまだ存在しなかった暗闇からもはや存在しない暗闇へと、私は流れ落ちていく。[中略]流れ落ちてゆくにまかせながら、何かを掴まなければ、その何かは永遠に失われてしまうと考えて私は脅えるが、その何かが何であるのかがわからない。私は単に消滅するのでない存在を求める」
(ヤスパース『哲学』)
単に消滅するのではない存在、つまり永遠的なるものに遭遇する在り方を、ロック・ギタリストのロバート・フィリップ(キング・クリムゾン)は、音楽家にふさわしく、次のように表現する。
「音楽家が得る唯一の報酬は音楽である。音楽がわれわれを覆い、われわれにその秘密をあかすとき、音楽の現前のただ中に立つという恩典である。同じことが聴衆にも言える。この瞬間に、他のすべての物事は色あせ、力を失う。音楽の中にいるこの者たちにとって、これこそ、人生が現実になる瞬間である」
(キング・クリムゾンの4枚組ライブCD『The Great Deceiver』の
ブックレット中のフィリップの文章)
初心とは、形式的に表せば、自らにとってAの報酬がAである、そうしたAに出会った心である。だが、こうした心をもってしても、人は、Bの報酬がCである、Cの報酬がDである、Dの報酬がEである…、というきりのない状況に、相変わらず絡めとられる。だからこの持続する状況を、Aの報酬がAであるという事態でもって突破してゆくこと、それが「希哲学」(philosophyの最初の訳語)たる哲学の、不断の課題となるのである。
(2023年6月1日)



親鸞仏教センター属託研究員
越部 良一
(KOSHIBE Ryoichi)
ヤスパースの『理性と実存』は、5つの講義から成り、その最初の講義でキルケゴールとニーチェをいわば同じ仲間として論ずる。しかし、この2人の何を同じだとしているのか、捉えるのは易しくない。ヤスパースの見る、2人を結び付けるものは、言葉を越えてゆくものなのだから。
ニーチェの思想を見る場合、永遠回帰とか超人とか力への意志とかに、キルケゴールでは、実存の三段階や絶望や不安などに眼をつけて、彼らの思想を捉えようとする、そうした仕方は普通にある。ヤスパースはここで、そうしたことへ深入りするそぶりが全くない。驚くべきことである。だがこの姿勢は、この2人の根本思考に厳密に忠実なのである。
「どこにも、有限性にも、意識的に把捉される根源にも、規定的に捉えられる超越者にも、歴史的な由来にも、最終的な支えは、彼らにとってはない」(ヤスパース『理性と実存』、越部良一訳、リベルタス出版、2023年。以下、引用はすべてこの拙訳から)。
ヤスパースが心底、眼を奪われているのは、彼らの規定されうるような諸思想ではなく、それらを越え包む何ものかである。
だから彼らの思考のいわば形、形式に、彼らの生き方、生きた形に眼をつける。例えばこうである。
「彼らにとって、ここでまた驚くべきことは、まさに彼らのできそこないの在り様それ自身が、彼ら特有の偉大さの条件であるということである。というのも、この偉大さは、彼らにとって、偉大さそのものではなく、時代状況に、その状況に固有なものとして属する、一回きりの偉大さなのであるから。注目すべきことは、いかに両者が、彼らの本質のこの側面に対しても、似たような比喩に思い至っているかである。ニーチェは自らをこう譬える、「でたらめな文字、見知らぬ力が、新しいペンを試すために紙の上に書く」。彼の病気の積極的な価値は、彼の絶えざる問題である。キルケゴールはしばしば思う、「神の暴力的な手によって抹消され、失敗した試みのように消し去られる」。彼は自らをまるで缶のふちに当って押し潰されるいわしのように感じる。彼に次のような思いが浮かぶ。「いつの代にも、他の人々の犠牲になり、ひどい苦悩のうちで他の人々に役立つものを……発見せねばならない2、3の人間がいるものだ」」。
この2人は現代ヨーロッパという時代と場所の「いわば代表的運命であり、犠牲者」なのである。しかも自ら進んで。「そのような犠牲なしでは決して気づくことはなかったであろう何ものか」、その前面には「何か途方もないこと」がある。ヤスパースは言う、「今の人は、過去の教説の全てを、書冊の意味では、以前の大哲学者たちの或る者が識っていたであろう以上に、ひょっとすると識っているかもしれない。しかし、教説に関する、そして歴史に関する、単なる知に変貌しているという意識、生それ自身から、そして事実信じられていた真理から解き放たれているという意識は、この伝統がいかに偉大であり、そして大きな満足を作り出してきたし、今も作り出していようとも、この伝統を、その究極的な意味において疑わしいものにしてきたのである。[中略]というのも、西洋の人間の現実のうちに、ひそかに、何か途方もないことが起っているからである。すなわち、あらゆる権威の崩壊、理性に対する溌剌たる信頼の徹底的な消滅、すべてを、全くもってすべてを可能にするように見える、結び付きの解消」。
実際上の無信仰のうちで、見かけ上何かを信じている風にすごしているという現代の状況、この状況の内にあって、「一方はキリスト教の信仰性をもち、他方は無神性を強調するという、まさに見かけ上は完全な本質相違性をもつから、それだけに彼らの思考の類似性は、ますます際立つものとなる。あたかもすべての過去のものがなおも存立しているかのような見かけのもと、実際は無信仰に生きているこの反省の時代において、信仰の拒否と自己を信仰へ強制することとは互いに属し合うものとなる。神なき者が信仰的に見え、信仰者が無信仰的に見えうる。両者は同じ弁証法のうちに立っている」。
現代の状況に沿いながら、その実、彼らが目指すものは、その状況がもつ、見かけ上の信仰と実際上の無信仰を、突破することなのである。この突破は、時代を超え、世界を超える。彼らは共に命がけの人間である。「彼らは一つの道を行くが、この道は、彼らにとっては、超越的な支えなくしては歩み通され得ない。というのも、彼らが反省するのは、平均的な現代性がするように、生命欲と生命関心という自明の限界をもってしてではないから。すべてか、しからずんば無か、それが問題である彼らは、限界のないことを敢えて行う。しかし、このことを彼らが行うことができるのは、ひとえに、彼らがはじめからあのものに根ざしているがゆえであり、それは、彼らにとっては同時に隠れているのである。すなわち、両名とも彼らの青年時代に、知られぬ神について言及している」。
「彼らの現存在の孤立無援、できそこなってあるものにして偶然的なもの、そうしたものと、彼らのもとで大きな対照をなしているのは、彼らを見舞うあらゆる出来事の意味、意義、必然性についての、人生が進むにつれ深まりゆく彼らの意識である。キルケゴールはそれを摂理と呼ぶ。彼は次のような神的なものをそこに認識する。「ここで起き、言われ、進行する等々すべてのことは、前兆であるということ、事実的なものは、それが何かはるかに高いものを意味するように、いつでも変貌するということ」」。
だからヤスパースは、彼ら自身では意識することが不可能な事実的なもの、彼らが40代でもう彼らの人生の突然の終りを迎えたこと等の、彼らの人生行路の共通性を指摘する。「まったく理解の無い反響に面するという運命も、彼らに共通であった」。彼らは、「この時代にとって、単に一つのセンセーションにすぎなかった」。「こうして彼らの影響力は、彼らの本質の、そして思考の意味に反して、限界なく崩壊させるものとなった」。彼らの交わりの追求は、だから、生前においてのみならず、死後もその趨勢において挫折した。
ヤスパースが見ようとするのは、彼らを包んでいる、知られぬあるものである。普通の、つまり、ただの人間的な見方では、例えば病気が「偉大さの条件」とされたりはしない。ここでは人間的視点を越えるものこそが、大なるものなのである。それが彼らを真に結び付ける。彼らが同じであることに驚くということは、そうしたものに、その者がふれているということであり、その知られぬものから問いかけられ、返答を迫られるということなのである。『理性と実存』という書物は、その返答の試みの書である。
この試みは、彼らの、掴みうるようにされた思想に従うことではあり得ない。彼ら自身がそのことをはねつける。「彼らは我々を立ち去らせる。我々にいかなる目標も与えず、いかなる規定された課題も立てはしない。個々の誰もが、彼らによって、自分自身であるものに成れるだけである」。
彼らを読むとは、そして彼らに対峙するこの書を読むこともまた、根本的に、その知られぬものに、自分自身が向かうということである。
(こしべ りょういち・親鸞仏教センター嘱託研究員)

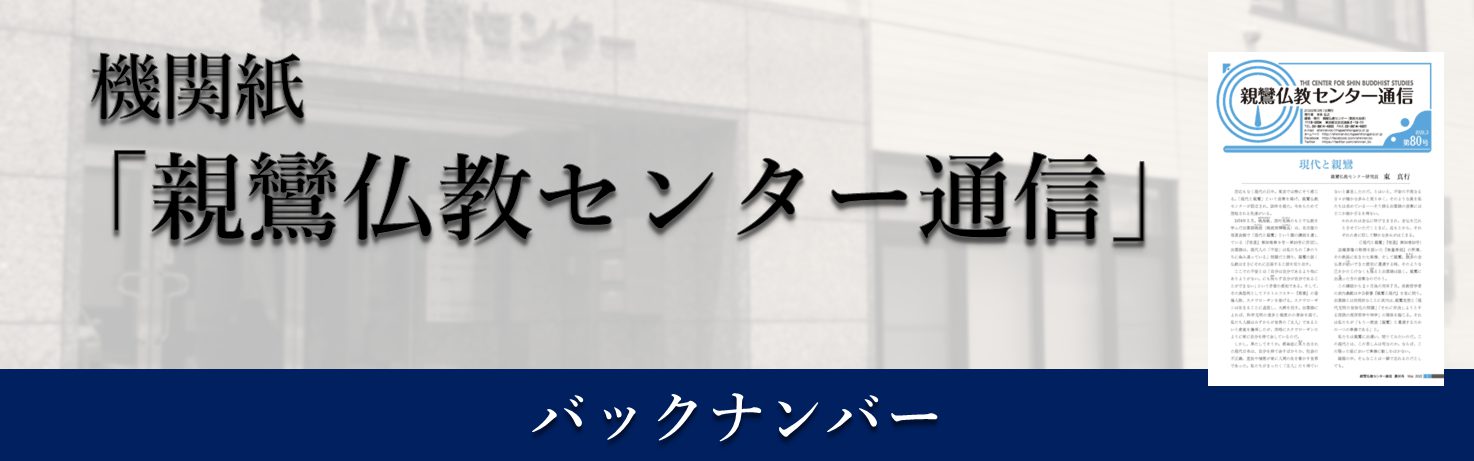
講師 本多 弘之 「涅槃、本当に生きることができる場所に立つ」
報告 越部 良一
講師 木村 哲也 「忘れられた存在を語り直す/忘れられた存在と出会い直す―ハンセン病問題と駐在保健婦―」
報告 菊池 弘宣
テーマ:近代の宗門教育制度と清沢満之
江島 尚俊 「明治前期・真宗大谷派における教育制度の特徴—他宗派との比較から考える―」
川口 淳 「メディアにみる大谷派教育と改革運動 —明治20年代の一考察」
藤原 智 「清沢満之と真宗大学(東京)の運営」
林 淳(コメンテーター)
東 真行(司会)
長谷川琢哉(開催趣旨・報告)
菊池 弘宣 「源空聖人の真像の銘文( 『選択集』 に関する銘文)③」
田村 晃徳 「寺川俊昭(1928〜2021)」



親鸞仏教センター嘱託研究員
越部 良一
(KOSHIBE Ryoichi)
今、ヤスパースの『理性と実存』を訳しているので、なぜ自分がこうしたことをしているのかを書いて見よう。
小林秀雄は言う、「本当にいい音楽とか、いい絵とかには、何か非常にやさしい[易しい]、当り前なものがあります。真理というものも、ほんとうは大変やさしく、単純なものではないでしょうか。現代の絵や音楽には、その単純なものが抜け落ちています。そしてそれは現代人の知恵にも抜けていることを、私は強く感じます」(国民文化研究会・新潮社編『小林秀雄 学生との対話』〔新潮社、2014〕 ※[ ]は引用者補足、以下同様)。
本当の哲学思想もおそろしく単純なものである。その単純なものを表現するのは難しい。否定的に表現する方が簡単である。例えば、法然流に言えば、哲学者(勿論、私のことではない)とは、「名聞・利養・勝他」によって動くことはない人のことである。複雑なものとは、ただ人に向う動きである。だから法然は「人にすぎたる往生のあた[仇(あだ)]はなし」(『法然上人絵伝』)と言う。だからといって、名聞、利養、勝他から遠ざかれば、そのおそろしく単純なやさしいものに近づくのかというと、そうとは限らない。それが単なる人の動きであれば同じことである。
だから、このおそろしく単純な事態を肯定的に表現すると、例えば、「自己自身に関わり、そのことによって己(おのれ)の超越者に関わる」(ヤスパース『哲学』)。しかし、どんな肯定的な表現も、また延々と説明できる。この表現でも「超越者」について。肯定的にして否定的に表現すると、例えばこうである。「[哲学の]語りにおいて、いつでも何か向け変えるものが存在し、その結果、存在の根拠が触れられるのは、むしろ、私がその根拠を捉えることのうちで、その根拠を名づけないことによってである。しかしこのことは再び、ただ次のときにのみある。私がその[名づける]ことを意図的に回避する――それは人為的な、単なる修辞的な文章技術である――のでなく、[この名づけないことを]全くもって意図されないものとして経験するときである。私が何に依って存在し、そして生きるのか、その何ものかを、私はただ次のようにしてのみ語ることができる。語られたものにおいて把握できる在り様ではそのものを逸し、そして、逸することによってそのものを間接的にまさに顕(あき)らかにする、というように」(『理性と実存』)。「向け変える」とは、魂を向け変えることである。名づけられるものから名づけられないものへ向け変えるのである。
大学院(早稲田大学)での恩師、伴博(ばん・ひろし)先生は、なぜ自分がヤスパースを好んで読むのかについて、哲学思想の力というものは、論理展開の厳密さや深さといったものでは測り切れないものだ、という意味のことを言っておられた。自分も又、ただひたすら、その測り知れぬ、単純なやさしいものに関わることを願うばかりである。
(2022年5月1日)

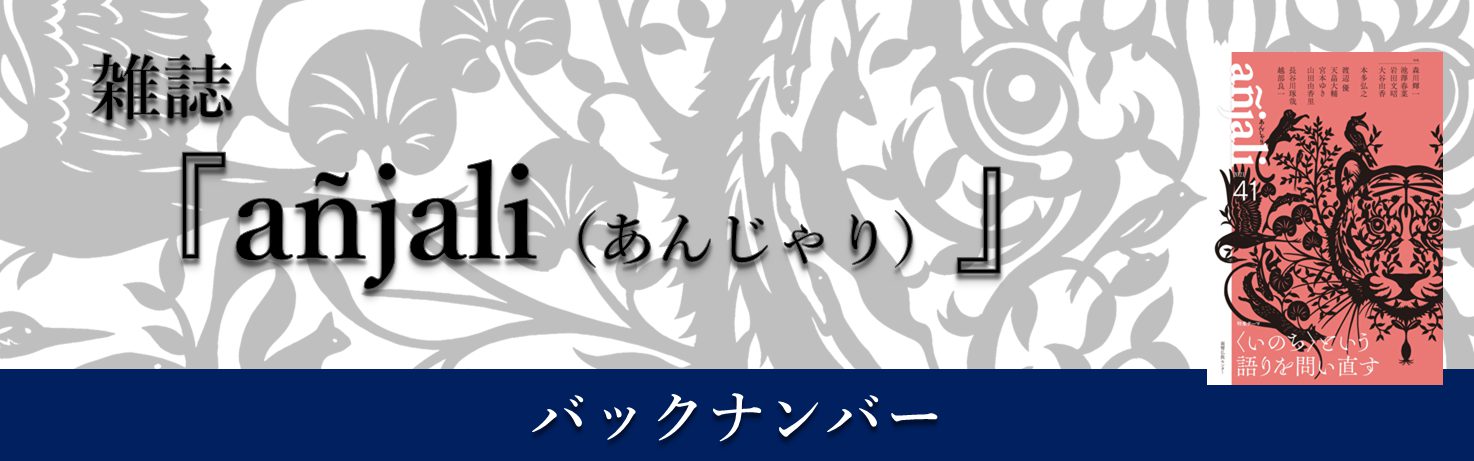

『アンジャリ』第41号
(2021年12月)
池澤 春菜 「ヒトのイノチの先に」
岩田 文昭 「いのちの否定と肯定」
大谷 由香 「日本仏教における「慈悲殺生」の許容」
天畠 大輔 「「あ、か、さ、た、な」で能力を考える」
宮本 ゆき 「核兵器と「悪」」
山田由香里 「祈りの造形を削り出す――鉄川与助の手仕事が生んだ聖なる空間」
※一部のコンテンツは無料でPDF版をご覧いただけます(タイトルをCLICK)


親鸞仏教センター嘱託研究員
越部 良一
(KOSHIBE Ryoichi)
「向(さき)に観察荘厳(しょうごん)仏土功徳成就と荘厳仏功徳成就と荘厳菩薩功徳成就を説きつ。この三種の成就は願心をして荘厳せりと、知るべし。略説して一法句に入るが故に。一法句とは、いはく清浄句なり。清浄句とは、いはく真実の智慧無為法身なるが故に」(天親『浄土論』)。浄土が「願心」であること、それが「仏」「菩薩」と「清浄」と「真実」「智慧」「無為」「法身」と「一」つであることが分かる。ところで法身とは仏の在り方のことで、「彼仏国土無為自然(じねん)」(『無量寿経』)であるから、「無為法身」とは阿弥陀仏のことである。「願生安楽国といふは、この一句はこれ作願門なり。天親菩薩の帰命の意なり」(曇鸞『浄土論註』)。この「作願」は「本願力回向」(『浄土論』)であるから、「帰命」(南無)は弥陀の願心である。願心は真実智慧であるから、「真実智慧無為法身」とは南無阿弥陀仏のことである。つまり、浄土とは南無阿弥陀仏である。何故に『浄土論』は著されたのか。「彼の安楽世界を観じて、阿弥陀如来を見たてまつり、彼の国に生まれんと願ずることを示現するが故なり。いかんが観じ、いかんが信心を生ずる」(同上)。これで願生の心が「信心」であると分かるから、「真実」は信心である。
以上、親鸞『顕浄土真実教行証文類』の「浄土真実」とは「願心」であり、「帰命」であり、「信心」である。すべて阿弥陀仏である。この『教行信証』の(『涅槃経』からの)引文、「真実といふは即ちこれ如来なり」、「大信心は即ちこれ仏性なり、仏性は即ちこれ如来なり」。『無量寿経』 に言う、法蔵菩薩は「この願を建て已(おわ)りて[中略]妙土を荘厳す。[中略]建立(こんりゅう)常然(じょうねん)にして、衰なく変なし」。法然は言う、「今、二種の信心を建立して、九品の往生を決定するものなり」(『選択集』)。善導は言う、「彼の仏、今、現に世に在(ましま)して成仏したまへり」(『往生礼讃』)。
浄土教における、この現生往生論にして現生成仏論を、ある種の死後往生、死後成仏論と対照してみよう。
一、前者は成仏を成仏土と捉える。それは一切衆生を体とする。成仏とは根本的には「彼仏今現在世成仏」、弥陀成仏以外にない。後者は成仏を個体に付ける。
二、前者は仏(=浄土)の本体、本性を、南無阿弥陀仏であり信心と捉える。後者は仏及び浄土の本性を、万善万行の円備と捉える。
三、前者は念仏(南無阿弥陀仏)を究極目的とし、万善万行を(その円備すらも)手段とする。後者は念仏を手段とし、万善万行の成就を究極目的とする。
四、前者の個体としての成仏(弥陀成仏中に存在する個体。弥陀の化身、化仏)は、他者に存在し、「自身」(他者から化身と見られる)としては罪悪の自覚である(善導の第一深信)。後者の成仏は、罪悪(煩悩)の完全な消滅、断滅の自覚であって、自身に存在する。
五、前者の仏は、(十劫の昔より)現在仏であると同時に、穢土に対しては本質的に菩薩である(浄土中の個体もそれに同ず)。後者の仏は本質的に菩薩でない。
浄土の思想は成仏観に革命をもたらし、一切衆生に現生成仏の道を開いてみせた。
(2021年7月1日)