
今との出会い第242回
「ネットオークションで出会う、アジアの古切手」
「ネットオークションで出会う、
アジアの古切手」

親鸞仏教センター嘱託研究員
伊藤 真
(ITO Makoto)
最近、ネットオークションで古い切手を競り落とすことにはまっている。私はデンマークの思想家キルケゴール(1813–55年)に関する本を読むのが好きで(研究ではなく単なる趣味だ)、関連情報をインターネットで検索することもあるせいか、ある日、パソコンの画面上に、デンマークの雑多な切手を袋詰めした商品の広告が表示された(検索履歴などに基づく「プッシュ型」の広告だ)。普段ならば無視してしまうが、少年時代に切手収集を趣味にしていた私は、何とはなしに広告をクリックしてみた。
切手収集の初心者がコレクションを始めるのに最初に買うような、文字通り二束三文と思われる古い記念切手や普通切手20〜30枚が袋詰めにされている。ところが広告の画像を拡大して切手を順に見ていくと、なんとそこにキルケゴールの肖像切手が1枚入っているではないか。調べてみると没後100年を記念した1955年の切手だが、普通切手と同じ小さなサイズで、地味なエンジ色の背景に晩年の冴えない肖像が使われている。だがそのみすぼらしい感じのするキルケゴールの切手との出会いに私は心を捉われ、初めてネットオークションに入札。雑多な袋詰め切手を買う人はいないとみえて、無事に落札した(実はその後、苦悶した才気煥発(さいきかんぱつ)な青年思想家時代の肖像を使った、2013年のキルケゴール生誕200周年の記念切手も入手した)。
それからというもの、長らく休眠していた切手収集という趣味の虫が半世紀ぶりに蠢(うごめ)きだした。だがネットオークションというのはどことなく危うい気もする。リアルな切手店とは異なり、売り手と買い手はネット上のオークション・サイトを通じてのみつながっていて顔も見えないし、オークションという性質上、競争心と購買意欲が——つまり我執や所有欲という煩悩が——煽られる。このため自分で入札は一件いくらまで、ひと月合計いくらまでと上限を設定して自制しつつ楽しんでいる。

さて、最近集めるようになったのは、東アジアや東南アジアのかつて欧米列強や日本の植民地支配を受けた地域の戦前・戦中の切手だ。郵便切手は1840年にビクトリア女王の肖像をデザインして英国で発行されたペニー・ブラックに始まり、まずは欧米から普及したが、アジアでも比較的早くから植民地政府により発行された。英領マレー(現在のマレーシアとシンガポールなど)、オランダ領東インド(蘭印、ほぼ現在のインドネシア)、スペイン領フィリピンなどでは1850–60年代にすでに本国の君主の肖像などをデザインしたものが発行され、フランス領インドシナ(仏印、現ベトナム、ラオス、カンボジア)などでも19世紀のうちに切手が登場している(日本は1871年)。19世紀や20世紀初頭の切手は実にクラシックな意匠や色調が美しく、惚れ惚れとして眺めているだけであっという間に時が過ぎてしまう(私は特に仏印や英領マレー、英領ビルマ[現ミャンマー(ビルマ)]などのエキゾチックな意匠のものが好きだ)。しかし同時に、植民地支配を受けたアジア諸国の歴史に思いを馳せる時、その美しさには悲しみが混じる。切手収集では一般的に未使用(ミントと言う)のものが価値が高いが、私は消印の押された使用済みのものをなるべく集めるようにしている。それは、実際に往時の人々が使った切手であり、人々の生活や時代の一端に触れることができる気がするからだ。だが戦前・戦中のアジア諸国の使用済み切手は、使った人が現地の人か支配者側かを問わず、列強の植民地支配下で営まれた生活の証であるだけに、いっそう複雑な思いを掻き立てるのだ。
アジア諸国の古切手の中でも、特に人々の運命の変転を感じるのは、「加刷(かさつ)」ものの切手に出会った時だ。「加刷」とは、急激なインフレ時や、特定の単価の切手が不足した時に、額面変更のために既存のデザインの切手に新たな単価などを上から重ねて印刷することだ。だがアジアの植民地時代の切手の場合、新たな支配者が自前の切手を発行できるようになるまでに、既存の切手にバッテン、消し線、その他の印や新たな国名や切手発行の意味合いなどを加刷し、暫定的に流通させたものがある。

例えば1942年に日本が占領した米領フィリピンでは、米国当局発行の切手に「祝バターン、コレヒドール陥落、1942」という何とも散文的な英文文字が加刷された(翌年には勇ましげな意匠に「フィリッピン郵便」「バターン、コレヒドール陥落一周年記念」という文言がヘンテコなカタカナの活字で記された切手が新たに発行され、以降「比島郵便」と刷られた各種切手が発行されていく)。英領マレーのイスラム文化の薫るモスクの切手や、支配者である英国王ジョージ6世の肖像に椰子の木をあしらった南国風な切手は、日本がマレー半島を占領した直後、国王の顔やモスクの上に「大日本郵便」という文字が「加刷」されて使用された。蘭印の切手でも、オランダのウィルヘルミナ女王の顔の上に刷られた日本の郵便マークや「大日本帝国郵便」の文字、日本語による地名表記などがまるで焼印のようだ。しかし、世の無常と言うべきか、(欧米列強も日本も)驕れる者は久しからずと言うべきか、蘭印では1945年、戦時中に日本当局が発行した切手の日本語部分を消し線で潰し、独立を宣言したインドネシア共和国がRepoeblik Indonesiaという赤い文字を加刷した切手が現れた。加刷切手は私たちに過去を見つめることを迫るのである。
一方、アジアの切手といえば、漫画『満州アヘンスクワッド』や昨年の直木賞・山田風太郎賞ダブル受賞作の小説『地図と拳』などで話題の「満州国」(正しくは「満洲国」)も興味深い。1932年、執政の地位に就いた愛新覚羅溥儀の肖像をあしらって「満洲国郵政」と刻した切手が発行された。その溥儀は、かつての清朝皇帝という仰々しいイメージではなく、洋装で現代風ではあるが、なぜかどこか心ここにあらずといった弱々しい風貌である。1934年に溥儀が満州国皇帝に即位すると、同じ意匠の切手に新たに「満洲帝国郵政」と記されるが、溥儀の肖像はそのままである。満州国の切手には別に「通郵」切手というものがある。国章の花がデザインされているが、満州国の「ま」の字も刷られていない。これは実は、満州国を承認しなかった中華民国宛の郵便専用に発行された切手だ。実務上、両国間の郵便を維持するための、苦肉の策だったのだろう。「五族協和」の「王道楽土」建設を標榜した満州国の通郵切手を見る時、私たちは何をどう思う(べき)だろうか。
アジアの珍しく、多くは美しい古切手との出会いには、歴史に触れる楽しみがあるが、それだけでなく、今を考えさせられることもある。例えば先述した蘭印のウィルヘルミナ女王の肖像切手。オランダ王国女王として1890–1948年と半世紀以上も王座にあったウィルヘルミナは(植民地主義国の君主ということの当否はともかくとして)、実はユリアナ、ベアトリクスと、2013年まで3代・125年近く続いたオランダの女王の時代の幕開けを飾った女性なのだ。この女王の肖像の頰に郵便マークを加刷した当時の大日本帝国は、言うまでもなく男性である裕仁(昭和)天皇の御世である。それから80年になろうとする今日の日本は、世界の男女平等度ランキングでひどく低迷したままで(国の順位の問題というより、実際は私たちが属する各種集団・組織のあり方や価値観が問われるのだが)、女性天皇をめぐる議論もいつの間にやら立ち消えになってしまったようである。アジアの美しくも悲しい古切手は、「今はどうなのか?」と、時には私たちに疑問も投げかけてくるのである。
(2023年10月1日)
最近、ネットオークションで古い切手を競り落とすことにはまっている。私はデンマークの思想家キルケゴール(1813–55年)に関する本を読むのが好きで(研究ではなく単なる趣味だ)、関連情報をインターネットで検索することもあるせいか、ある日、パソコンの画面上に、デンマークの雑多な切手を袋詰めした商品の広告が表示された(検索履歴などに基づく「プッシュ型」の広告だ)。普段ならば無視してしまうが、少年時代に切手収集を趣味にしていた私は、何とはなしに広告をクリックしてみた。
切手収集の初心者がコレクションを始めるのに最初に買うような、文字通り二束三文と思われる古い記念切手や普通切手20〜30枚が袋詰めにされている。ところが広告の画像を拡大して切手を順に見ていくと、なんとそこにキルケゴールの肖像切手が1枚入っているではないか。調べてみると没後100年を記念した1955年の切手だが、普通切手と同じ小さなサイズで、地味なエンジ色の背景に晩年の冴えない肖像が使われている。だがそのみすぼらしい感じのするキルケゴールの切手との出会いに私は心を捉われ、初めてネットオークションに入札。雑多な袋詰め切手を買う人はいないとみえて、無事に落札した(実はその後、苦悶した才気煥発(さいきかんぱつ)な青年思想家時代の肖像を使った、2013年のキルケゴール生誕200周年の記念切手も入手した)。
それからというもの、長らく休眠していた切手収集という趣味の虫が半世紀ぶりに蠢(うごめ)きだした。だがネットオークションというのはどことなく危うい気もする。リアルな切手店とは異なり、売り手と買い手はネット上のオークション・サイトを通じてのみつながっていて顔も見えないし、オークションという性質上、競争心と購買意欲が——つまり我執や所有欲という煩悩が——煽られる。このため自分で入札は一件いくらまで、ひと月合計いくらまでと上限を設定して自制しつつ楽しんでいる。
さて、最近集めるようになったのは、東アジアや東南アジアのかつて欧米列強や日本の植民地支配を受けた地域の戦前・戦中の切手だ。郵便切手は1840年にビクトリア女王の肖像をデザインして英国で発行されたペニー・ブラックに始まり、まずは欧米から普及したが、アジアでも比較的早くから植民地政府により発行された。英領マレー(現在のマレーシアとシンガポールなど)、オランダ領東インド(蘭印、ほぼ現在のインドネシア)、スペイン領フィリピンなどでは1850–60年代にすでに本国の君主の肖像などをデザインしたものが発行され、フランス領インドシナ(仏印、現ベトナム、ラオス、カンボジア)などでも19世紀のうちに切手が登場している(日本は1871年)。19世紀や20世紀初頭の切手は実にクラシックな意匠や色調が美しく、惚れ惚れとして眺めているだけであっという間に時が過ぎてしまう(私は特に仏印や英領マレー、英領ビルマ[現ミャンマー(ビルマ)]などのエキゾチックな意匠のものが好きだ)。しかし同時に、植民地支配を受けたアジア諸国の歴史に思いを馳せる時、その美しさには悲しみが混じる。切手収集では一般的に未使用(ミントと言う)のものが価値が高いが、私は消印の押された使用済みのものをなるべく集めるようにしている。それは、実際に往時の人々が使った切手であり、人々の生活や時代の一端に触れることができる気がするからだ。だが戦前・戦中のアジア諸国の使用済み切手は、使った人が現地の人か支配者側かを問わず、列強の植民地支配下で営まれた生活の証であるだけに、いっそう複雑な思いを掻き立てるのだ。
アジア諸国の古切手の中でも、特に人々の運命の変転を感じるのは、「加刷(かさつ)」ものの切手に出会った時だ。「加刷」とは、急激なインフレ時や、特定の単価の切手が不足した時に、額面変更のために既存のデザインの切手に新たな単価などを上から重ねて印刷することだ。だがアジアの植民地時代の切手の場合、新たな支配者が自前の切手を発行できるようになるまでに、既存の切手にバッテン、消し線、その他の印や新たな国名や切手発行の意味合いなどを加刷し、暫定的に流通させたものがある。
例えば1942年に日本が占領した米領フィリピンでは、米国当局発行の切手に「祝バターン、コレヒドール陥落、1942」という何とも散文的な英文文字が加刷された(翌年には勇ましげな意匠に「フィリッピン郵便」「バターン、コレヒドール陥落一周年記念」という文言がヘンテコなカタカナの活字で記された切手が新たに発行され、以降「比島郵便」と刷られた各種切手が発行されていく)。英領マレーのイスラム文化の薫るモスクの切手や、支配者である英国王ジョージ6世の肖像に椰子の木をあしらった南国風な切手は、日本がマレー半島を占領した直後、国王の顔やモスクの上に「大日本郵便」という文字が「加刷」されて使用された。蘭印の切手でも、オランダのウィルヘルミナ女王の顔の上に刷られた日本の郵便マークや「大日本帝国郵便」の文字、日本語による地名表記などがまるで焼印のようだ。しかし、世の無常と言うべきか、(欧米列強も日本も)驕れる者は久しからずと言うべきか、蘭印では1945年、戦時中に日本当局が発行した切手の日本語部分を消し線で潰し、独立を宣言したインドネシア共和国がRepoeblik Indonesiaという赤い文字を加刷した切手が現れた。加刷切手は私たちに過去を見つめることを迫るのである。
一方、アジアの切手といえば、漫画『満州アヘンスクワッド』や昨年の直木賞・山田風太郎賞ダブル受賞作の小説『地図と拳』などで話題の「満州国」(正しくは「満洲国」)も興味深い。1932年、執政の地位に就いた愛新覚羅溥儀の肖像をあしらって「満洲国郵政」と刻した切手が発行された。その溥儀は、かつての清朝皇帝という仰々しいイメージではなく、洋装で現代風ではあるが、なぜかどこか心ここにあらずといった弱々しい風貌である。1934年に溥儀が満州国皇帝に即位すると、同じ意匠の切手に新たに「満洲帝国郵政」と記されるが、溥儀の肖像はそのままである。満州国の切手には別に「通郵」切手というものがある。国章の花がデザインされているが、満州国の「ま」の字も刷られていない。これは実は、満州国を承認しなかった中華民国宛の郵便専用に発行された切手だ。実務上、両国間の郵便を維持するための、苦肉の策だったのだろう。「五族協和」の「王道楽土」建設を標榜した満州国の通郵切手を見る時、私たちは何をどう思う(べき)だろうか。
アジアの珍しく、多くは美しい古切手との出会いには、歴史に触れる楽しみがあるが、それだけでなく、今を考えさせられることもある。例えば先述した蘭印のウィルヘルミナ女王の肖像切手。オランダ王国女王として1890–1948年と半世紀以上も王座にあったウィルヘルミナは(植民地主義国の君主ということの当否はともかくとして)、実はユリアナ、ベアトリクスと、2013年まで3代・125年近く続いたオランダの女王の時代の幕開けを飾った女性なのだ。この女王の肖像の頰に郵便マークを加刷した当時の大日本帝国は、言うまでもなく男性である裕仁(昭和)天皇の御世である。それから80年になろうとする今日の日本は、世界の男女平等度ランキングでひどく低迷したままで(国の順位の問題というより、実際は私たちが属する各種集団・組織のあり方や価値観が問われるのだが)、女性天皇をめぐる議論もいつの間にやら立ち消えになってしまったようである。アジアの美しくも悲しい古切手は、「今はどうなのか?」と、時には私たちに疑問も投げかけてくるのである。
(2023年10月1日)
最近の投稿を読む

著者別アーカイブ
- 今との出会い第234回「「適当」を選ぶ私」
- 今との出会い 第230回「本願成就の「場」」
- 今との出会い 第222回「仏教伝道の多様化にいかに向き合うか」
- 今との出会い 第221回「「自由」と「服従」」
- 今との出会い 第218回「思惟ということ」
- 今との出会い 第220回「そういう状態」
- 今との出会い 第211回「#Black Lives Matter ――差別から思うこと」
- 今との出会い 第210回「あの時代の憧憬」
- 今との出会い 第207回「浄土の感覚」
- 今との出会い 第202回「「救い」ということ」
- 今との出会い 第200回「そもそも王舎城で―マガダ国王・頻婆娑羅(ビンビサーラ)考―」
- 今との出会い 第199回「曖昧なブラック」
- 今との出会い 第198回「一瞬の同時成立」
- 今との出会い 第196回「ともしびとなる日々」
- 今との出会い 第194回「星の祝祭を手のひらに」
- 今との出会い 第192回「「共感」の危うさ」
- 今との出会い 第190回「再び王舎城へ―阿難最後の願いと第一結集の開催―」
- 今との出会い 第186回「人生、なるようにしか……」
- 今との出会い 第184回「ひとりの夢を」
- 今との出会い 第182回「遺伝性の疾患等の理由で強制不妊手術が行われていたという報道に触れて思うこと」
- 今との出会い 第180回「地涌の菩薩」をどう読むか
- 今との出会い 第176回「自分との対話」
- 今との出会い 第174回「そしてハイシャはつづく」
- 今との出会い 第172回 「劉暁波氏の訃報にふれて思うこと」
- 今との出会い 第170回「現代へのまなざし」
- 今との出会い 第166回「独り立つ「人」」
- 今との出会い 第164回「誰かと生きる時間」
- 今との出会い 第163回「市場経済とペットの命」




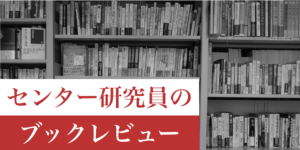
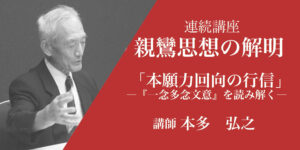




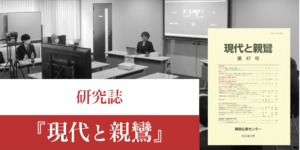


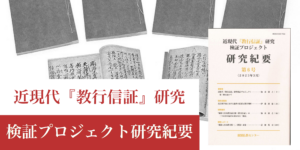

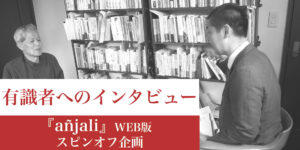





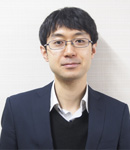


 続いて、北朝鮮側が遠望できる「DMZ展望台」を訪れた。デッキへ出ると、運良く快晴となった青空の下に緑の大地が北方へと続いていた(曇天だと国境の向こうは見えないという)。手すりに沿って何台も並ぶ見学用の双眼鏡で覗くと、北朝鮮側のDMZの内外に作られた国策村の家々や、DMZの向こう側の高層住宅、さらには南北融和の象徴だったが今や機能停止している開城(ケソン)工業団地の一部が遠望できた。銃声もプロパガンダ放送の音もしない、静かな美しい緑豊かな大地のわずか数キロ先に、政治的・経済的統制下で暮らすことを強いられている人々の日常がある……それを想像するのは何とも非現実的な感覚だった。57年前の厳冬の夜、「38度線」から転戦してベトナム戦争の前線へ派遣されるのではとの恐怖に、やむにやまれず徒歩で密かに国境線を越えて逃亡したジェンキンス軍曹の姿も、思い浮かべることは難しかった。見学を終え、「今晩は繁華街の明洞(ミョンドン)でどんな韓国料理を食べようかな」などと考えながら、韓国の自由のすばらしさを思ったが、その自由の裏には時が止まったように70年間も続く南北の分断と対立・緊張の現実があること、そして自由な韓国に暮らす人々の「同胞」が(さらに拉致被害者の方たちも)北朝鮮の圧政下に日々を
続いて、北朝鮮側が遠望できる「DMZ展望台」を訪れた。デッキへ出ると、運良く快晴となった青空の下に緑の大地が北方へと続いていた(曇天だと国境の向こうは見えないという)。手すりに沿って何台も並ぶ見学用の双眼鏡で覗くと、北朝鮮側のDMZの内外に作られた国策村の家々や、DMZの向こう側の高層住宅、さらには南北融和の象徴だったが今や機能停止している開城(ケソン)工業団地の一部が遠望できた。銃声もプロパガンダ放送の音もしない、静かな美しい緑豊かな大地のわずか数キロ先に、政治的・経済的統制下で暮らすことを強いられている人々の日常がある……それを想像するのは何とも非現実的な感覚だった。57年前の厳冬の夜、「38度線」から転戦してベトナム戦争の前線へ派遣されるのではとの恐怖に、やむにやまれず徒歩で密かに国境線を越えて逃亡したジェンキンス軍曹の姿も、思い浮かべることは難しかった。見学を終え、「今晩は繁華街の明洞(ミョンドン)でどんな韓国料理を食べようかな」などと考えながら、韓国の自由のすばらしさを思ったが、その自由の裏には時が止まったように70年間も続く南北の分断と対立・緊張の現実があること、そして自由な韓国に暮らす人々の「同胞」が(さらに拉致被害者の方たちも)北朝鮮の圧政下に日々を