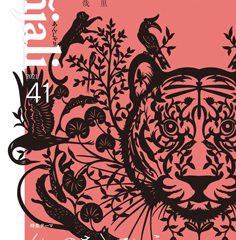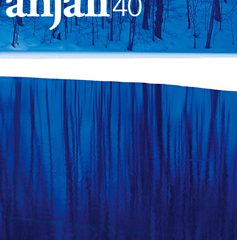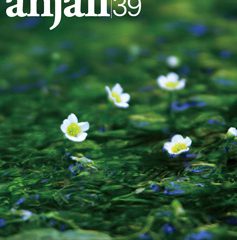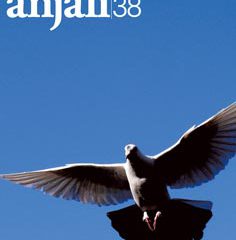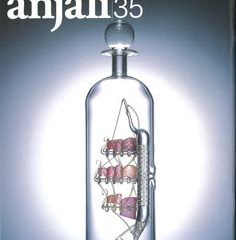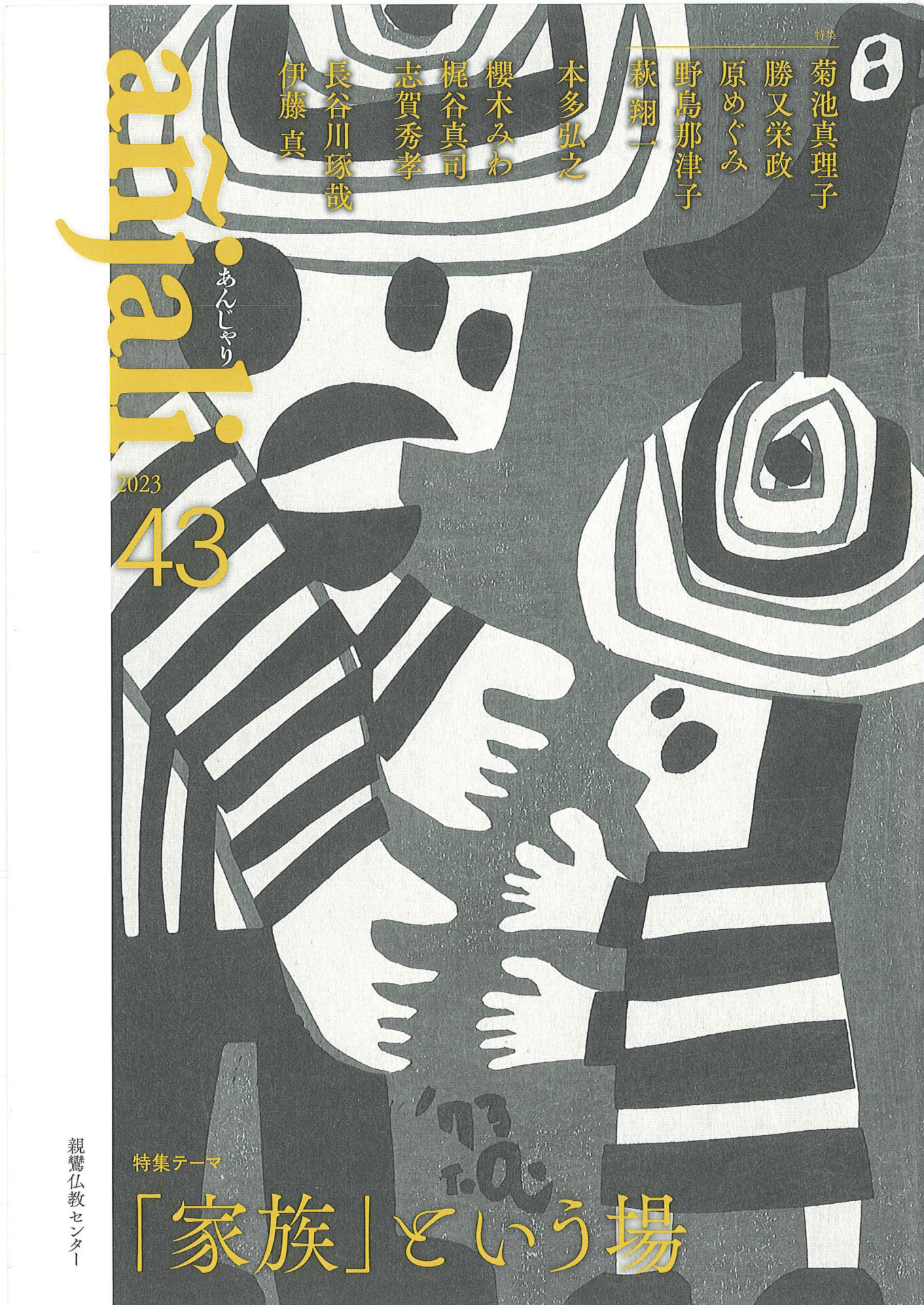
『アンジャリ』第43号
(2023年12月)
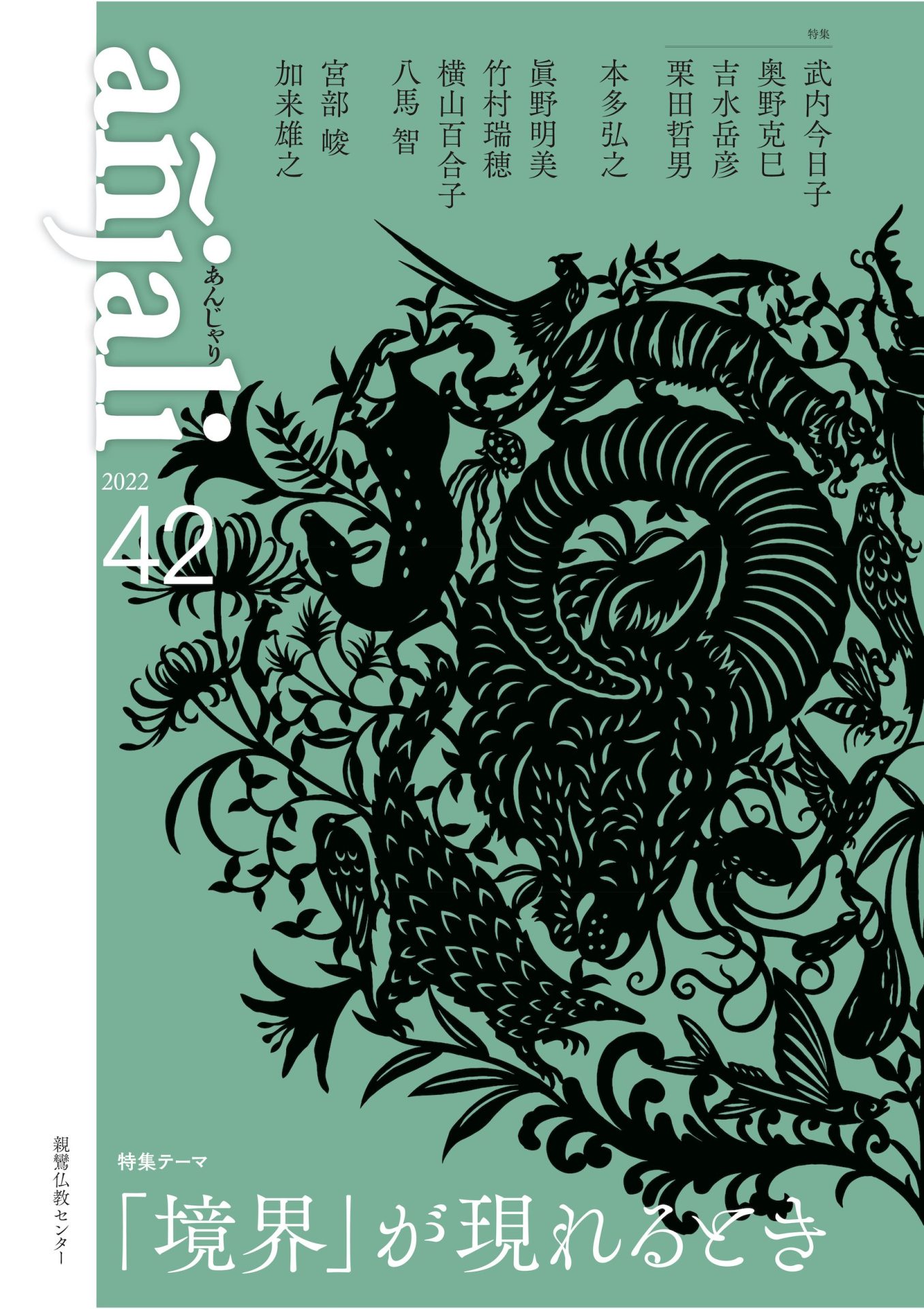
『アンジャリ』第42号
(2022年12月)
奥野 克巳 「境界なき世界の往還と他力――浄土思想からアニミズムを読み解く――」
吉水 岳彦 「慈愛の境界」
栗田 哲男 「「チベット」という語に潜む固定観念」
眞野 明美 「ウィシュマさんが生きていけた社会」
竹村 瑞穂 「スポーツの意味と美しさについて」
横山百合子 「「日記」を書く遊女たち」
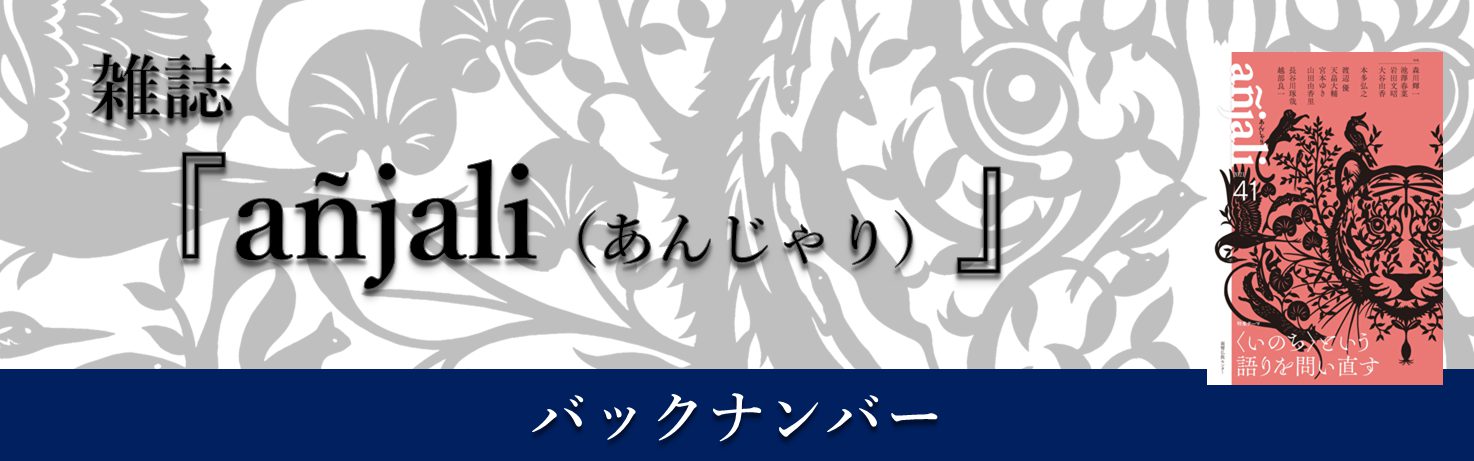

『アンジャリ』第41号
(2021年12月)
池澤 春菜 「ヒトのイノチの先に」
岩田 文昭 「いのちの否定と肯定」
大谷 由香 「日本仏教における「慈悲殺生」の許容」
天畠 大輔 「「あ、か、さ、た、な」で能力を考える」
宮本 ゆき 「核兵器と「悪」」
山田由香里 「祈りの造形を削り出す――鉄川与助の手仕事が生んだ聖なる空間」
※一部のコンテンツは無料でPDF版をご覧いただけます(タイトルをCLICK)
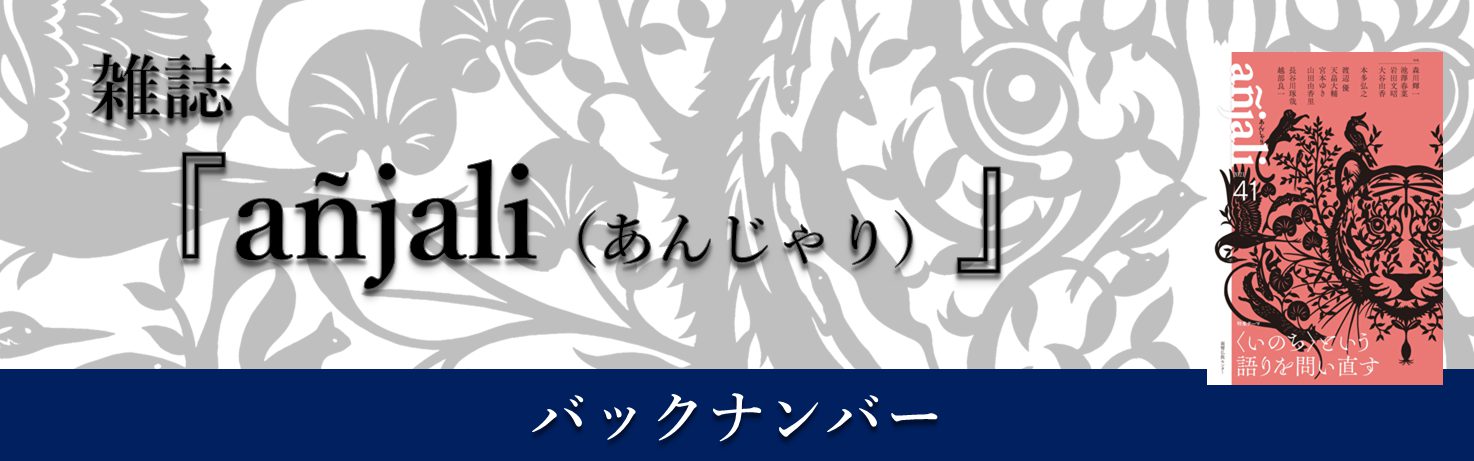
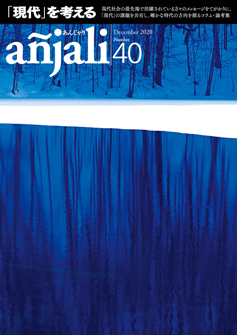
『アンジャリ』第40号
(2020年12月)
千代 豪昭 「優生学の反省と医療倫理」
松尾 剛次 「寺子屋こども大学と東日本大震災」
吉田 千亜 「言葉に敏感であることの大切さ――原発事故の加害と被害を忘れないために」
大城 聡 「「裁判員経験」と「共有」」
木村 哲也 「〈来者〉とはだれか――分断を超えるハンセン病文学の言葉」
藤村 潔 「扇の学び」
※一部のコンテンツは無料でPDF版をご覧いただけます(タイトルをCLICK)
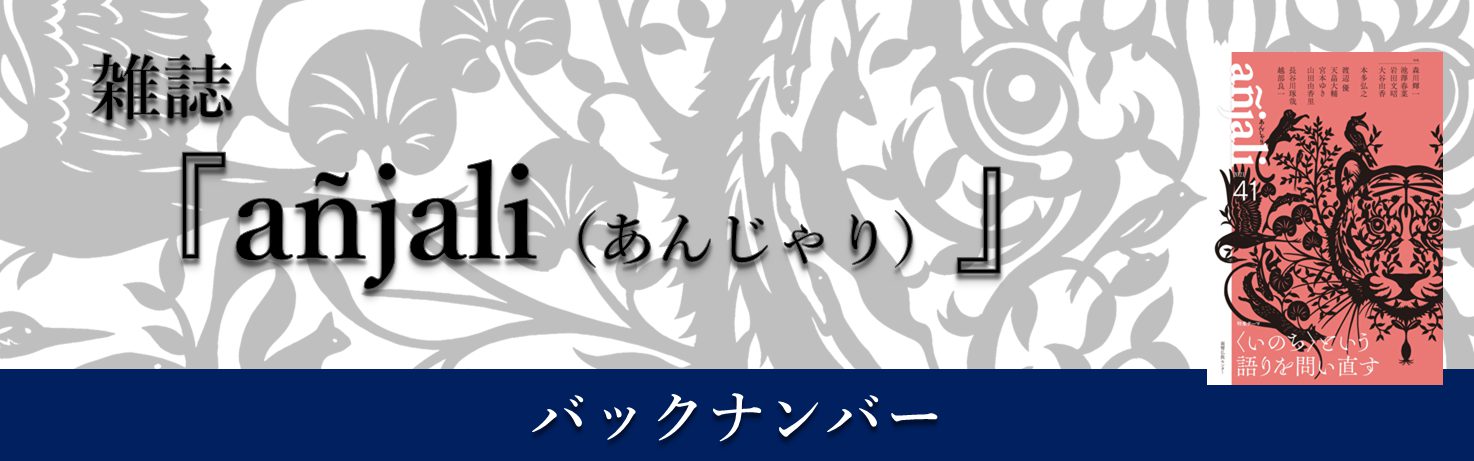

『アンジャリ』第39号
(2020年6月)
伊藤 真 「「近代」と「私」三題――「九」がつく年・ディストピアSF・お地蔵さん」
一ノ瀬正樹 「死者のかすかな存在性」
安藤 泰至 「いのちを語る、いのちが語る」
サンキュータツオ 「「ヘンな論文」から見た日本の研究・研究者のおもしろさとは?」
岸野 亮示 「開律院釋龍山:西本龍山が遺したもの」
野村佐紀子 「GO WEST」
伊藤 聡 「中世神道とその研究の軌跡」
速水 馨 「『añjali』の編集方針について」
※一部のコンテンツは無料でPDF版をご覧いただけます(タイトルをCLICK)
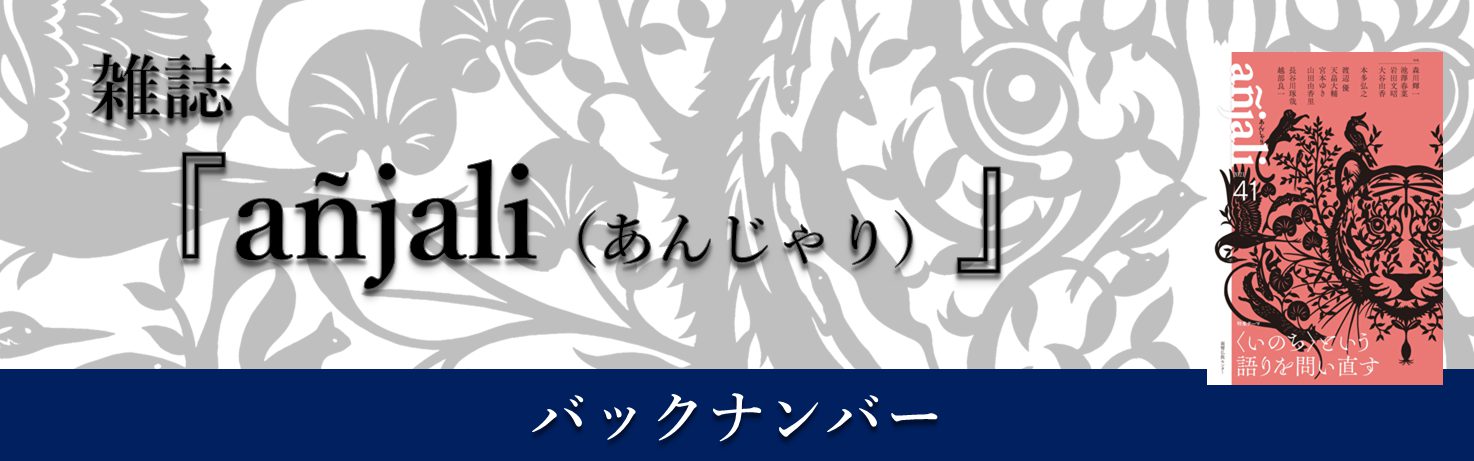
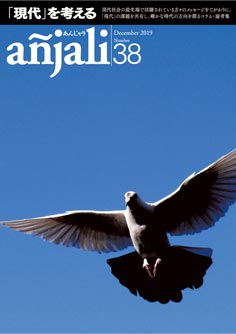
『アンジャリ』第38号
(2019年12月)
嶽本あゆ美 「解き放たれて、浄土を生きる」
菅尾健太郎 「世界宗教としての浄土真宗とその開教」
山田 慎也 「社会に適合した葬送墓制の構築へ」
林 智裕 「「人殺し」と呼ばれて――福島に暮らす原発事故被災者は、なぜ「悪人」にされたのか
土屋 太祐 「那辺と這辺――幻覚と真実の間」
出口 治明 「日本の課題とこれからの大学」
木下 光生 「自己責任が大好きな日本人たちへ」
東 真行 「泥凡夫」
※一部のコンテンツは無料でPDF版をご覧いただけます(タイトルをCLICK)
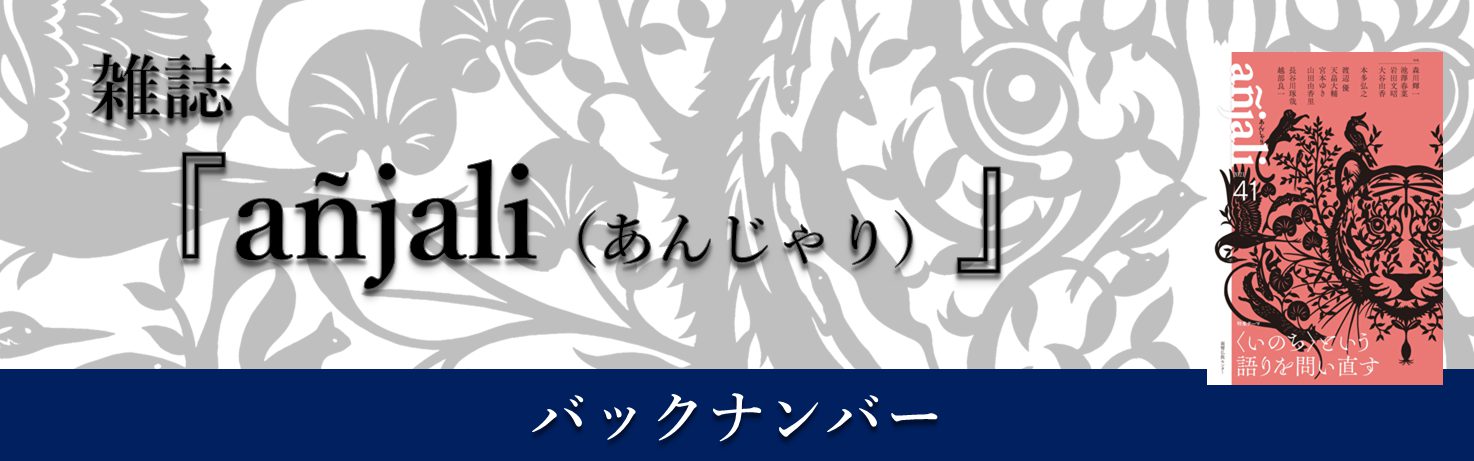

『アンジャリ』第37号
(2019年6月)
本間 美穂 「当事者の声の聞かれ方」
宝生 和英 「強かな中世――真の文化の多様性に向けて――」
栗原裕一郎 「緊縮は人心のデフレ、お金は愛」
山野 浩一 「「吉本隆明」という名の安心感」
佐藤 研 「キリスト教徒の禅」
早坂 類 「的となるべきゆふぐれの水」
中村 玲太 「無辺の大地を想え」
※一部のコンテンツは無料でPDF版をご覧いただけます(タイトルをCLICK)
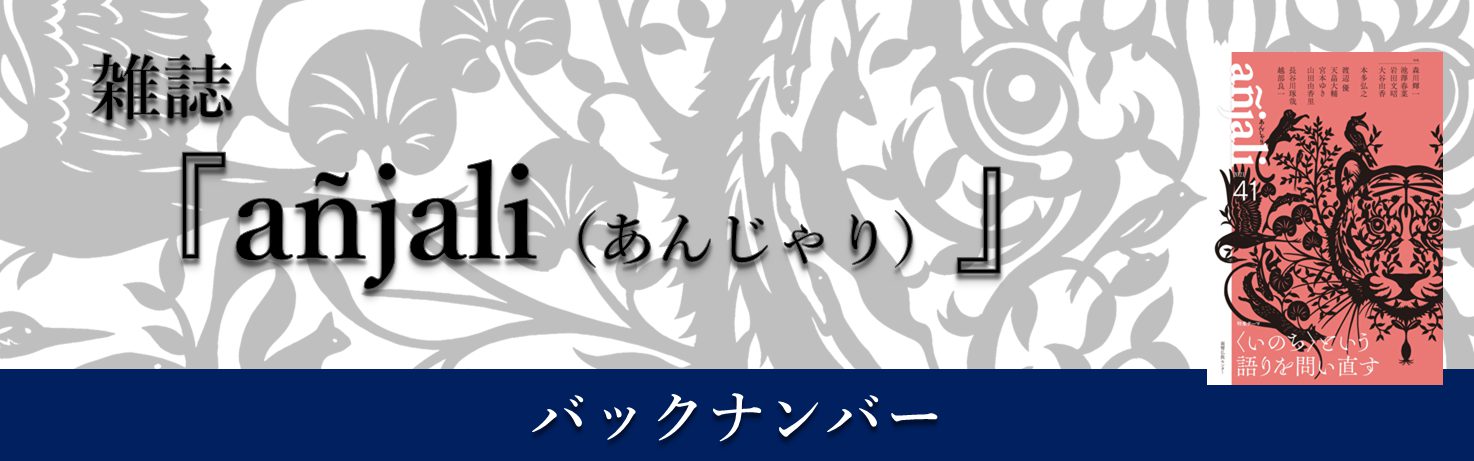

『アンジャリ』第36号
(2018年12月)
飯田 一史 「「すべて私が悪い」という「逃げ」を拭う――『聲の形』論――」
宮崎 学 「死は次なる生命を支える」
松尾 剛次 「寺子屋こども大学と東日本大震災」
田原 牧 「彼女の役割」
伊藤由紀夫 「非行少年を鏡として」
谷釜 了正 「躍動する「いのち」―スポーツの効能を考える―」
辻 浩和 「遊女の信心」
松本 紹圭 「ポスト宗教時代、仏教の挑戦」
菊池 弘宣 「「被害者感情」が本当にどう解けていくのか」
※一部のコンテンツは無料でPDF版をご覧いただけます(タイトルをCLICK)
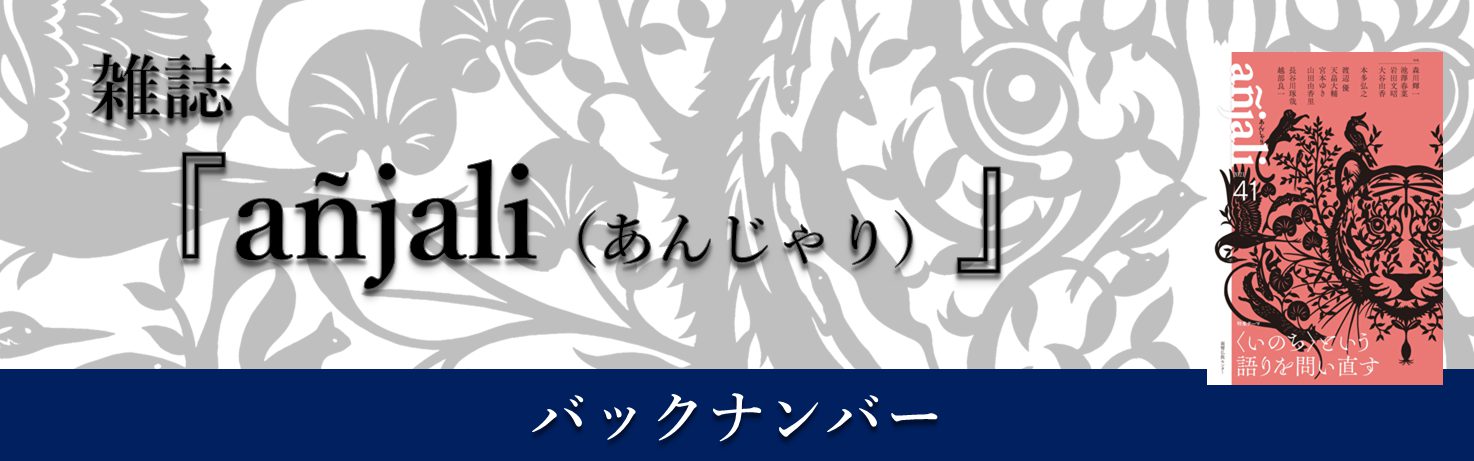
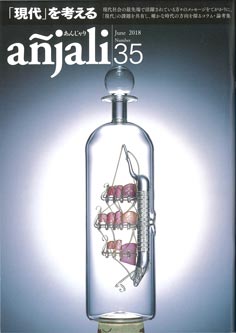
『アンジャリ』第35号
(2018年6月)
彌永 信美 「「東洋学」の発展的解体に向けて―「自分史」から回顧しつつ」
石井 公成 「「厩戸王」騒動が示すもの」
水野 和夫 「資本主義の終焉とこれからの社会」
杉山登志郎 「児童精神科の外来から見えるもの」
岡 檀 「生き心地の良さとは何か―日本で“最も”自殺の少ない町の調査から」
三上 修 「仏と神と鳥類多様性」
坂口 幸弘 「亡き人の生きた証の伝承」
戸次 顕彰 「「大比丘衆千二百五十人」考」
※一部のコンテンツは無料でPDF版をご覧いただけます(タイトルをCLICK)
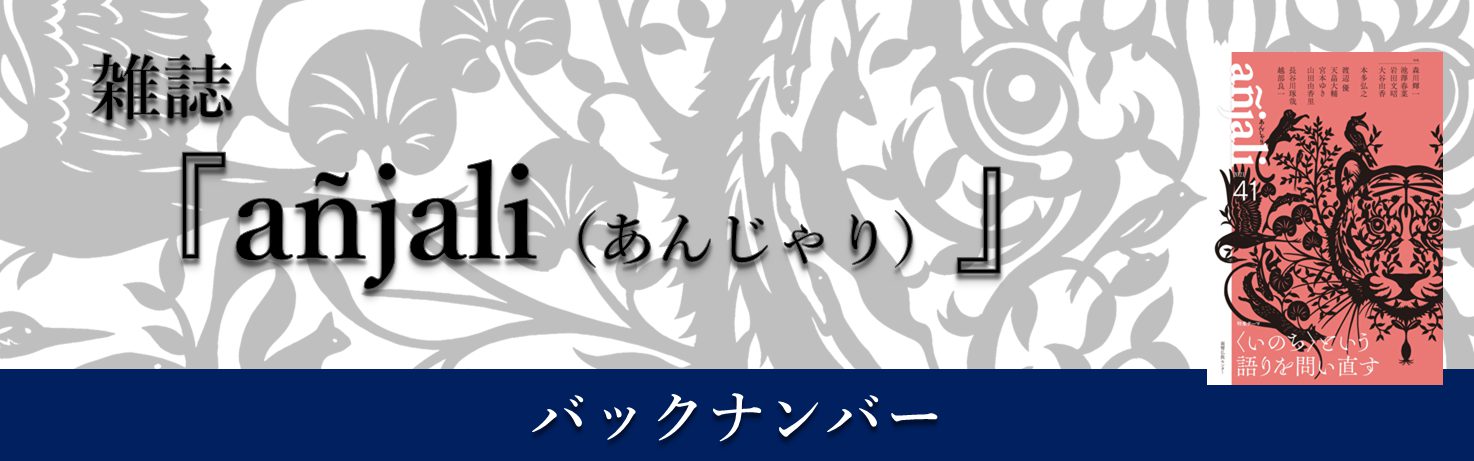
彌永 信美 「「東洋学」の発展的解体に向けて―「自分史」から回顧しつつ」
石井 公成 「「厩戸王」騒動が示すもの」
水野 和夫 「資本主義の終焉とこれからの社会」
杉山登志郎 「児童精神科の外来から見えるもの」
岡 檀 「生き心地の良さとは何か―日本で“最も”自殺の少ない町の調査から」
三上 修 「仏と神と鳥類多様性」
坂口 幸弘
亡き人の生きた証の伝承
戸次 顕彰 「「大比丘衆千二百五十人」考」
※一部のコンテンツは無料でPDF版をご覧いただけます(タイトルをCLICK)
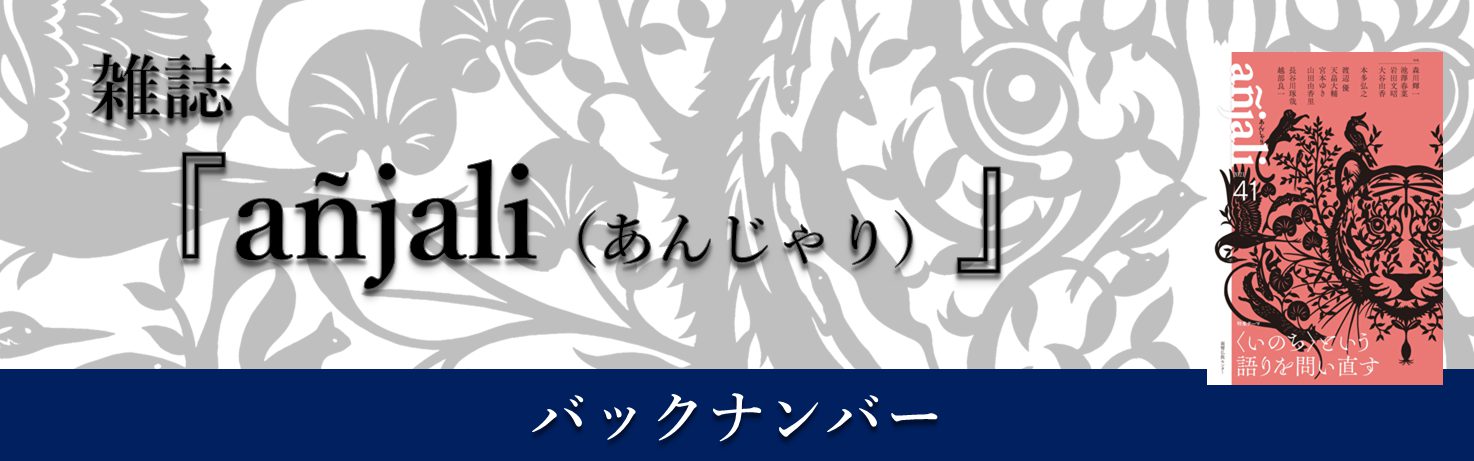

『アンジャリ』第34号
(2017年12月)
井上 智洋 「人工知能がもたらす労働のない社会」
山内 志朗 「雪と重力」
福嶋 聡 「書店は、劇場である」
木村 草太 「法教育の重要性」
さとうまきこ 「三十五年前の個人面談」
岸上 仁 「いのちの根源的連帯を求めて」
吉永 進一 「大拙研究の新展開――日文研国際シンポジウム「鈴木大拙を顧みる:没後五十年を記念して」に出席して」
飯島 孝良 「或る夏の「帰郷」」
※一部のコンテンツは無料でPDF版をご覧いただけます(タイトルをCLICK)