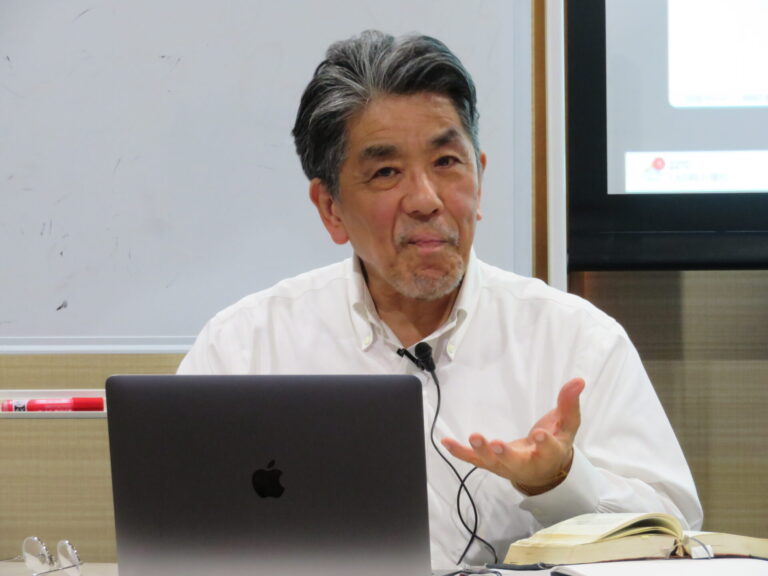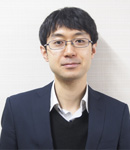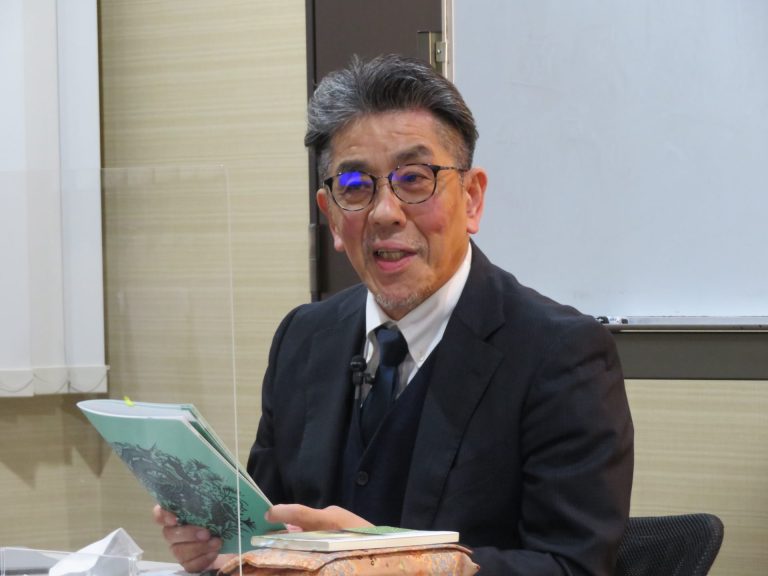今との出会い第250回
「〈心〉のありか」への旅
2025年5月22日、親鸞仏教センターにおいて、脳科学者の恩蔵絢子氏と劇作家の嶽本あゆ美氏をお招きして、第72回現代と親鸞の研究会「〈心〉のありか——アルツハイマー型認知症に問われて」を開催した。
アルツハイマー型認知症が問題となるのは、記憶と能力が失われることによって、自身のアイデンティティーや親しい人との関係が崩れていくことをめぐる煩悶と、またその人との関係を構築し直す生々しい営みが、そこに存在するからであろう。両氏は、このアルツハイマー型認知症という現実をどのように受けとめるかについて、それぞれのお立場から知見をお示しくださった。
恩蔵氏は、脳の機能を人類の脳・ほ乳類の脳・は虫類の脳という三層で捉えることで「その人らしさ」を成り立たせる〈心〉のありかを「感情」に見出すことができることを、嶽本氏は、私たちの「愛」を成り立たせるような〈心〉のありかを、個人の心理のうちにとどめず社会的存在の関係の間(あわい)から見直すことを提言された。
両氏の専門的な知識、生々しい体験と実践、実証例にもとづく発表はきわめて説得力に満ち、私たちの心に響くものがあった(『親鸞と現代』53号に研究会報告を掲載予定)。
研究会を縁に私が一仏教徒として「〈心〉のありか」について考えたことを、できるだけ専門用語を使わずに、述べてみたい。
苦悩する自己の実存的・存在論的意味を問うてきた仏教は、脳の機能という生理的・心理的次元にも、また人間関係という社会的次元にも還元することができない〈心〉の次元を問題としているように思う。
〈心〉には、たとえば知情意というような心理作用に解消されてしまうことのない、何か底しれない深さがある。人間の愛憎や悲哀がとどかない深い場所という生の感覚が成り立つような〈心〉の深い層がある。
私たちは、人の世において、さまざまな愛憎に苦しみ、戦争や災害などによる困難で苛酷な状況を生きなければならないが、そのとき、そのような苦難を乗り越えたいという願いや祈りを生みだしてくる場という次元の〈心〉がある。
私はそのような〈心〉を、私たちの経験のすべてを成り立たせ、引き受けている場としての〈心〉であると考えたい。いま、ここに、私として、さまざまな他者や事物と関わっている、この身という不可思議な事実を受けとめるという次元で成り立つ〈心〉である。どのような現実であってもそれをそのまま受けとめている身の事実に相応する〈心〉である。
その〈心〉は、私たちがそれを意識しようとしまいと私たちが生きていることの根底に厳然と存在する。それは、どのような人間や社会の濁りも悪も悲惨もそのままに引き受けている〈心〉の場と表現してもよい。
そしてその〈心〉こそ、そのまま人間の苦難を正しく受けとめる祈り、願い、そして覚悟や自覚が成り立つ場でもあるにちがいない。
たとえば、仏教徒の私にとってその〈心〉は、私たちがブッダの教えによって呼びかけられているという歴史的社会的な事実を受けとめる場として存在している。そしてそのような場としてある〈心〉が、思いを離れることのきない私たちに如来の願いを受けとめることを可能にする。仏教には、そのような〈心〉のありかを探究する伝統が確かに存在する。
とくに親鸞の思想を学ぶ私にとって、その〈心〉はどのような絶望的な状況になってもその事実を事実のままに受けとめて崩れない信知が成り立つ場としてある。このような〈心〉を明らかにしたいという切実な要求が、私の親鸞の思想についての学びを突き動かしてきた。
この深い次元の〈心〉については、科学的・実証的な立場から語ることは難しいが、私たちの自己・他者・世界の見え方や受けとめ方(この人世に処する心構え)に決定的な影響を及ぼすのではないかと思う。もちろん、この〈心〉が、どこまで現代人に必要とされるのか、またそのような問いが具体的な困難や苦悩の中にある人にどのような実践的な意味をもつのか、分からない。しかし、そのような「〈心〉のありか」がはっきりしなければ、少なくとも仏教を学ぶ者としてアルツハイマー型認知症という現実にきちんと向き合えないのではないかと感じるのである。
今日、人間とは何かがあらためて根底から問われている。たとえばAIが人間に取って代わるという危機意識に動揺する私たちがいる。しかし、もしその危機感が知識や能力に立った浅薄な人間観にもとづいているならば、それこそ人間の「〈心〉のありか」を見失う危機だと言うことができる。
今、私たちは、仏教が明らかにしてきた深い〈心〉のありかへの旅を求められているのかもしれない。
元大谷大学文学部真宗学科教授。
大谷大学名誉教授。
現在、親鸞仏教センター副所長。
過去の投稿を読む
著者別アーカイブ
-
- 今との出会い第236回「想いだされ続けるということ――「淵源(ルーツ)」を求めて」
- 今との出会い 第225回「「一休フェス〜keep on 風狂〜」顛末記」
- 今との出会い 第214回「二十年前、即今に在り」
- 今との出会い 第201回「演じる―山崎努と一休に寄せて―」
- 今との出会い 第191回「「寝業師」根本陸夫―「道」を求めし者たちが交わらせるもの―」
- 今との出会い 第181回「 “We shiver and welcome fire” ―シカゴ印象記―」
- 今との出会い 第171回「無知を「批判」的に自覚する契機―「浪人」ということについて―」
- 今との出会い 第162回「遊ぶ子どもの声きけば」
-
- 今との出会い第234回「「適当」を選ぶ私」
- 今との出会い 第230回「本願成就の「場」」
- 今との出会い 第222回「仏教伝道の多様化にいかに向き合うか」
- 今との出会い 第221回「「自由」と「服従」」
- 今との出会い 第218回「思惟ということ」
- 今との出会い 第220回「そういう状態」
- 今との出会い 第211回「#Black Lives Matter ――差別から思うこと」
- 今との出会い 第210回「あの時代の憧憬」
- 今との出会い 第207回「浄土の感覚」
- 今との出会い 第202回「「救い」ということ」
- 今との出会い 第200回「そもそも王舎城で―マガダ国王・頻婆娑羅(ビンビサーラ)考―」
- 今との出会い 第199回「曖昧なブラック」
- 今との出会い 第198回「一瞬の同時成立」
- 今との出会い 第196回「ともしびとなる日々」
- 今との出会い 第194回「星の祝祭を手のひらに」
- 今との出会い 第192回「「共感」の危うさ」
- 今との出会い 第190回「再び王舎城へ―阿難最後の願いと第一結集の開催―」
- 今との出会い 第186回「人生、なるようにしか……」
- 今との出会い 第184回「ひとりの夢を」
- 今との出会い 第182回「遺伝性の疾患等の理由で強制不妊手術が行われていたという報道に触れて思うこと」
- 今との出会い 第180回「地涌の菩薩」をどう読むか
- 今との出会い 第176回「自分との対話」
- 今との出会い 第174回「そしてハイシャはつづく」
- 今との出会い 第172回 「劉暁波氏の訃報にふれて思うこと」
- 今との出会い 第170回「現代へのまなざし」
- 今との出会い 第166回「独り立つ「人」」
- 今との出会い 第164回「誰かと生きる時間」
- 今との出会い 第163回「市場経済とペットの命」