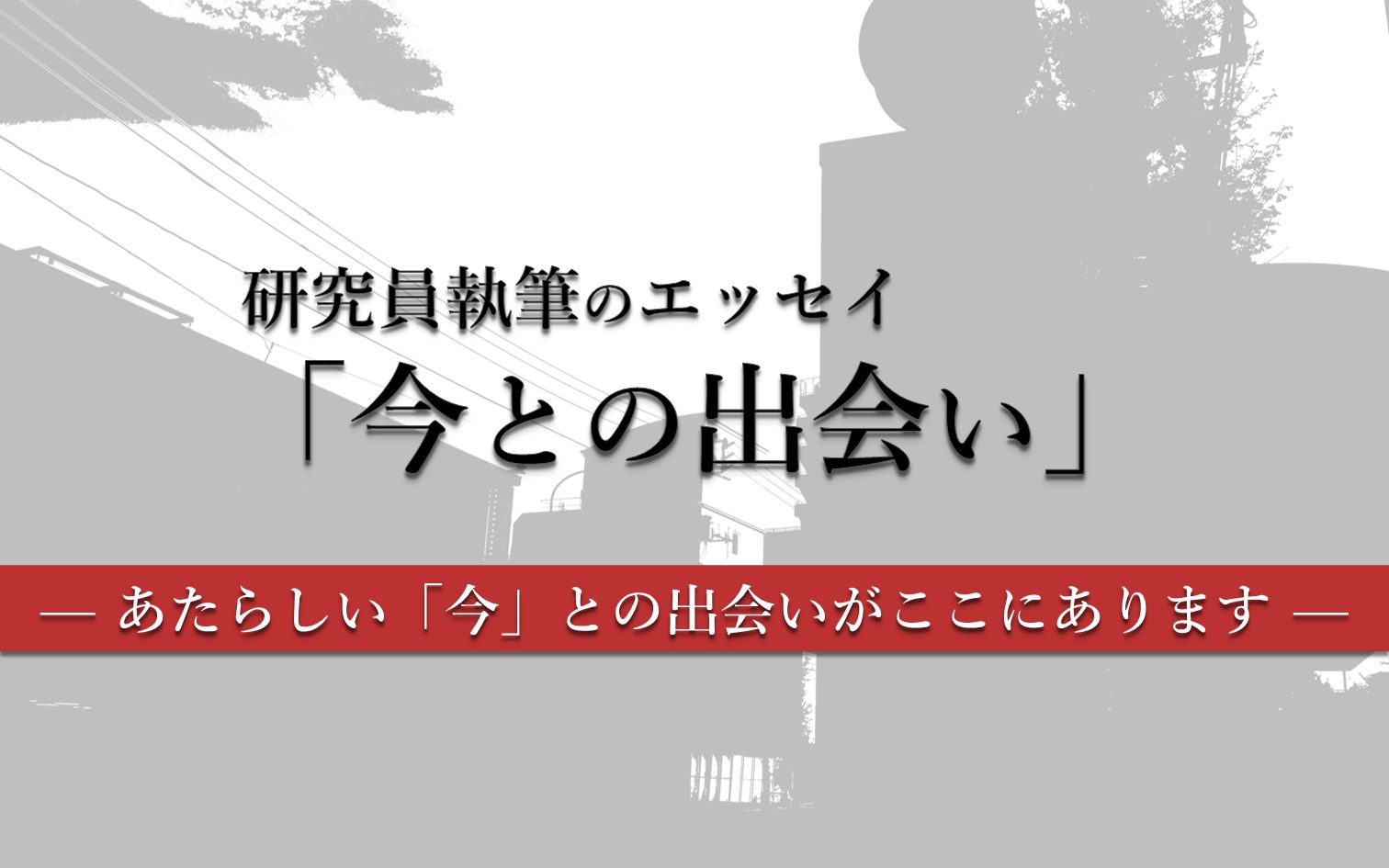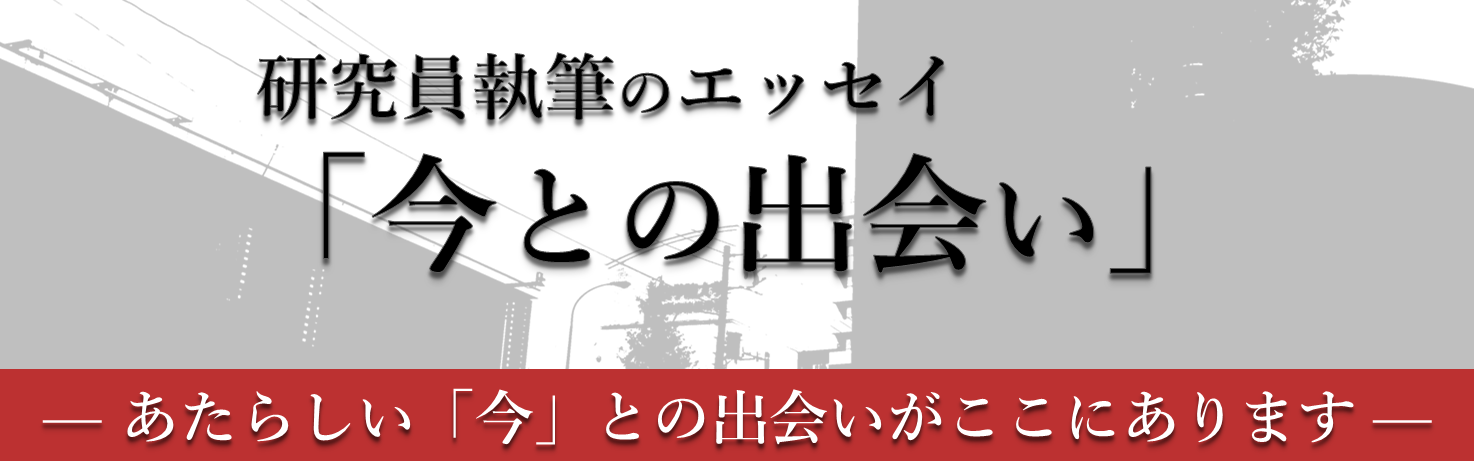
今との出会い第185回「深さの次元」

親鸞仏教センター嘱託研究員
田村 晃徳
(TAMURA Akinori)
人間の生はもはや深みの次元においてではなく、水平線的な次元において営まれる。「さらにより多く」「さらにより大きく」「さらによりよく」というような言い方が、この水平線的な方向をあらわす徴候である。
(「失われた次元」『ティリッヒ著作集』第4巻 白水社 60頁)
平成がもうすぐ終わろうとしている。突然、終わってしまった昭和とは異なり、終了までの猶予が与えられている希(まれ)な時代として平成は記憶されるであろう。
この30年間の特記すべき事柄としては、インターネットの普及による生活の劇的変化があげられる。インターネットは世界をコンパクトにした。グローバル化という言葉は決して絵空ごとではなく、現実にそうなっている。世界の状況を私たちは瞬時に知ることができる。また、何かほしいものがあればネット上からクリックすれば楽に手にすることができる。それを可能としたのは、人間の「もっともっと」という発想であろう。「もっと早く」「もっと安く」「もっと楽に」・・・このように平成の30年間は、日本も世界も「もっともっと」の追求と実現により進んできた。
しかし、それは上のティリッヒの言葉によれば、水平線的方向である。平成という時代を「平らに成った」と読むのならば、まさに時代の特徴を言い当てているだろう。私たちは水平線的に生きるものとなった。「もっともっと」への推進力が、私たちの生活をかたどっている。
だが、ティリッヒは私たちが忘れている次元を指摘する。それは「深みの次元」である。「深みの次元」の喪失とは何を意味するのか。
それが意味するところは、人間が、自己の生の意味に関する問いに対し答えを失ったということである。その問いとは、人間はどこから来てどこへ行くのか、人間は誕生と死とのあいだの短い期間のなかで何を行ない何をつくり出さねばならないかという問いである。
(同上58頁)
水平線的生に慣れたものにとり、このような問いは出すことさえ難しい。しかし、私たちはどこまでいっても、欲望が止むことはない以上、生の満足には大きな軸の転換が必要である。深さの次元の喪失に気づくことは、私たちが見失ったものを知ると同時に、本来有していた次元に気づくことでもある。「深さ」の探求こそが生の充実を与えるのだろう。
ティリッヒは「深さの次元」への問いこそが宗教的な問いであるとした。その指摘を受けるとき、「深信自信」「深広無境涯底」など、真宗がいかに深さの探求を述べていたのかについてあらためて気づく。「深さの次元」の提示は、新たな元号の時代となる今後、ますます大切な言葉となるに相違ない。
(2018年10月1日)
最近の投稿を読む

今との出会い 第232回「漫画の中の南無阿弥陀仏」
2022年9月09日
今との出会い 第232回「漫画の中の南無阿弥陀仏」 親鸞仏教センター嘱託研究員 青柳 英司 (AOYAGI Eishi) 日本の仏教史において、南無阿弥陀仏という言葉が持った意味は極めて重い。 この六字の中に、法然は阿弥陀仏の「平等の慈悲」を発見し、親鸞は一切衆生を「招喚」する如来の「勅命」を聞いた。彼らの教えは、身分を越えて様々な人の支援を受け、多くの念仏者を生み出すことになる。そして、現代においても南無阿弥陀仏という言葉は僧侶だけが知る特殊な用語ではない。一般的な国語辞典にも載っており、広く人口に膾炙(かいしゃ)したものであると言える。…
続きを読む

今との出会い 第231回「病に応じて薬を授く」
2022年8月01日
今との出会い 第231回「病に応じて薬を授く」 親鸞仏教センター主任研究員 加来 雄之 (KAKU Takeshi) 「また次に善男子、仏および菩薩を大医とするがゆえに、「善知識」と名づく。何をもってのゆえに。病を知りて薬を知る、病に応じて薬を授くるがゆえに。」(『教行信証』化身土巻、『真宗聖典』354頁)…
続きを読む

今との出会い 第230回「本願成就の「場」」
2022年6月01日
今との出会い 第230回「本願成就の「場」」 親鸞仏教センター嘱託研究員 中村 玲太 (NAKAMURA Ryota) 「信仰を得たら何が変わりますか?」――訊ねられる毎に苦悶する難問であり、断続的に考えている問題である。これは自身の研究課題とする西山義祖・證空(1177…
続きを読む

今との出会い 第229回「哲学者とは何者か」
2022年5月01日
今との出会い 第229回「哲学者とは何者か」 親鸞仏教センター嘱託研究員 越部 良一 (KOSHIBE Ryoichi) 今、ヤスパースの『理性と実存』を訳しているので、なぜ自分がこうしたことをしているのかを書いて見よう。…
続きを読む
No posts found