今との出会い第243回「磁場に置かれた曲がった釘」

今との出会い第243回「磁場に置かれた曲がった釘」 親鸞仏教センター主任研究員 加来 雄之 (KAKU Tak…
『親鸞仏教センター通信』第86号

『親鸞仏教センター通信』第86号 掲載Contents PDFで全紙面を開く 巻頭言 「私にとっての「現場」」…
今との出会い第240回「真宗の学びの原風景」

今との出会い第240回「真宗の学びの原風景」 親鸞仏教センター主任研究員 加来 雄之 (KAKU Takesh…
『近現代『教行信証』研究検証プロジェクト研究紀要』第6号
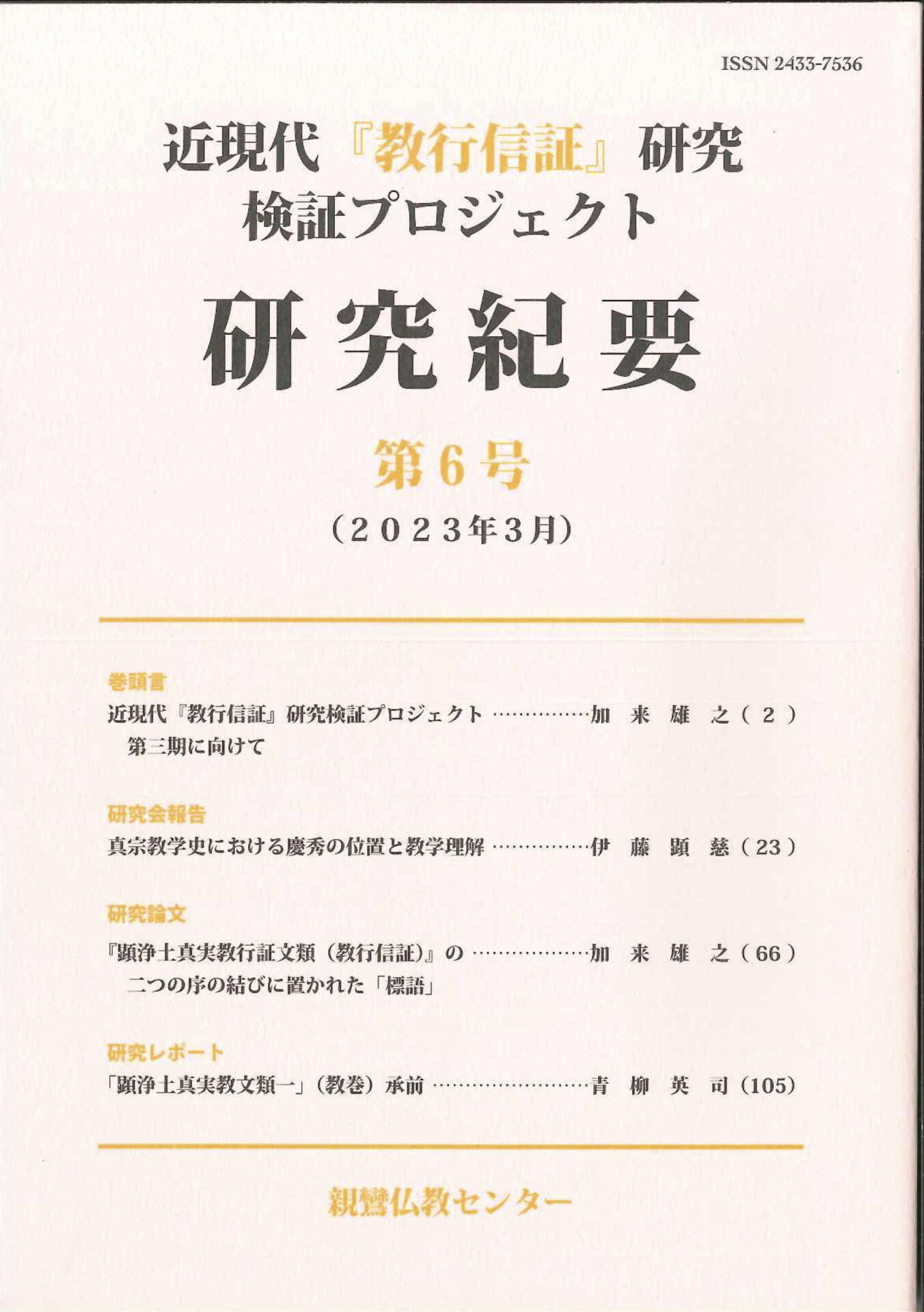
『近現代『教行信証』研究検証プロジェクト研究紀要』第6号 掲載Content ■ 研究会報告 加来 雄之 「近…
『親鸞仏教センター通信』第85号
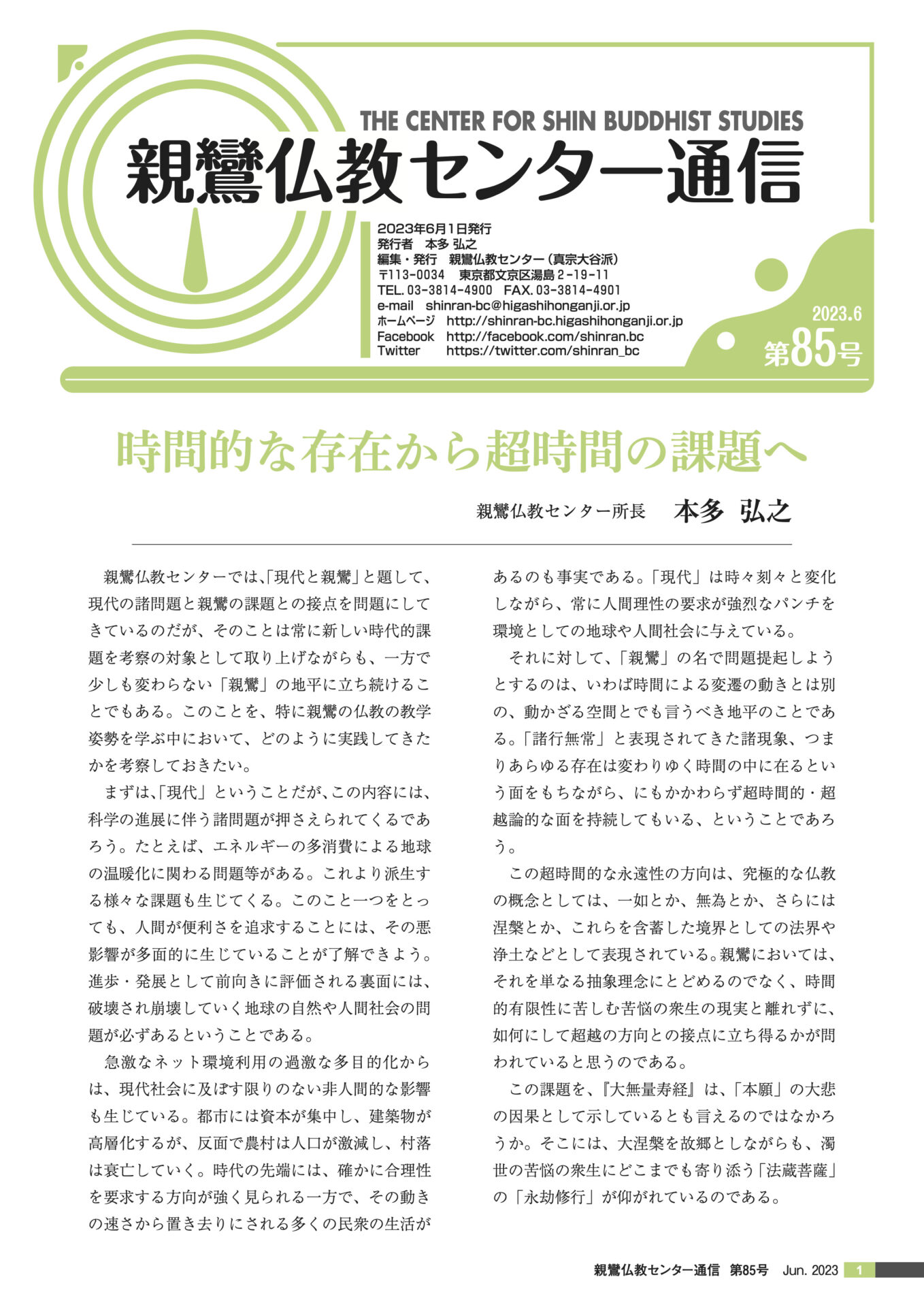
『親鸞仏教センター通信』第85号 掲載Contents PDFで全紙面を開く 巻頭言 本多 弘之 「時間的な存…
『アンジャリ』WEB版(2023年5月1日更新号)

『アンジャリ』WEB版(2023年5月1日更新号) 目次 インドで年越し蕎麦を啜る インドで年越し蕎麦を啜る …
念仏機

念仏機 親鸞仏教センター主任研究員 加来 雄之 (KAKU Takeshi) どのような時代でも、どのような…
『アンジャリ』第42号
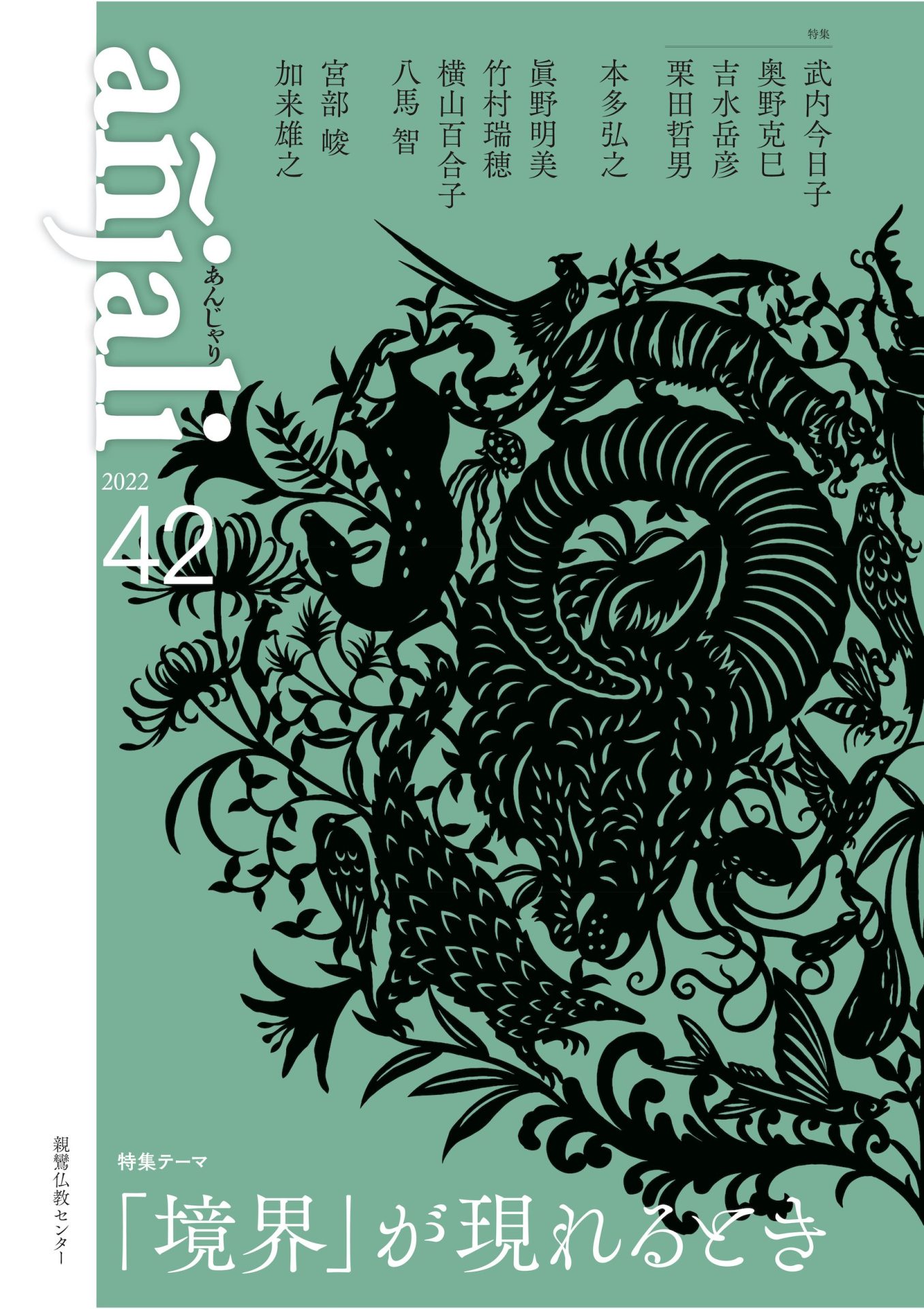
『アンジャリ』第42号 (2022年12月) ■ 特集「「境界」が現れるとき」 宮部 峻 「「境界」が現れる…
「親鸞仏教センター通信」第82号

「親鸞仏教センター通信」第82号 掲載Contents PDFで全紙面を開く 巻頭言 加来 雄之 「思想の「場…
今との出会い 第231回「病に応じて薬を授く」

今との出会い 第231回「病に応じて薬を授く」 親鸞仏教センター主任研究員 加来 雄之 (KAKU Takes…